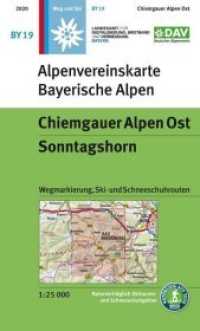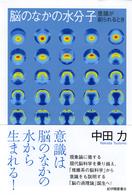出版社内容情報
自治体の子ども・子育て支援部門に初めて配属されたあなたへ──
この1冊が「安心のスタート」をお約束します!
子ども・子育て支援の基礎から、現場で役立つ実践、制度の要点まで、現役公務員がやさしい言葉でナビゲート。
「福祉部門ははじめてで不安…」
「制度がたくさんあって難しそう…」
「手続きが複雑そうで頭が痛い…」
そんな不安・悩みをまるごとフォローします。
◎基礎知識をゼロから整理
図解を交えた仕組みと背景の解説で、しっかり把握できる
◎制度のポイントをピックアップ
重要な関係法規をおさえ、日々の業務にスムーズに適用できる
◎現場で使える実践ノウハウを解説
相談対応や事務処理など、子ども・子育て支援特有のスキルを習得できる
配属直後のおともとして、また日々の手続きチェックに、制度の学び直しにも活用できる一冊。
子ども・子育て支援の全体像をしっかりつかみ、あなたの「現場力」をぐっと引き上げます!
【目次】
はじめに
凡例
第1章 子ども・子育て支援部門へようこそ
1-1 子ども・子育て支援担当の仕事って?
1-2 「子ども・子育て支援」とは何か
1-3 常に「子どもの最善の利益」を第一に
1-4 子ども・子育て支援は積極的な連携で成り立つ
1-5 自治体間の分担と行政機関の役割
COLUMN 1 こども家庭庁
第2章 担当者が心得るべき仕事の初手
2-1 良質な窓口対応・住民対応の実践ポイント
2-2 実地訪問が現場の理解につながる
2-3 相談対応がうまくいく「連携」のコツ
2-4 法規の理解が子育て支援事務の土台になる
2-5 子ども・子育て支援法の要点をおさえる
2-6 知っておきたい子ども・子育ての重要トピック11
COLUMN 2 悪質なクレームや不当要求行為
第3章 母子保健
3-1 すべての子どもが健やかに育つ社会をつくる
3-2 母子保健担当が読むべき関係法規
3-3 健康診査・検査の業務
3-4 保健指導などの業務
3-5 医療対策などの業務
3-6 「児童福祉」との一体的な支援の進め方
COLUMN 3 育児休業
第4章 家庭での子育てと子ども育成支援
4-1 家庭での子育てを支え、学齢期の子どもを育む
4-2 読んでおくべき子育て支援事業の関係法規
4-3 家庭での子育てを支える事業と業務
4-4 学齢期の子どもを支える業務
COLUMN 4 子ども・子育て支援と学校教育との連携
第5章 幼児教育・保育
5-1 乳幼児期の育ち・学びを保障する
5-2 幼児教育・保育の重要な関係法規
5-3 多様な施設類型を覚えよう
5-4 自治体が行う計画・施設のマネジメント
5-5 教育・保育の利用に関する事務
5-6 充実した保育サービスの取組み
5-7 家庭と支援サービスをつなぐ窓口対応のコツ
COLUMN 5 幼児期と小学校の育ち・学びをつなげる取組み
第6章 障がいのある子どもへの支援
6-1 すべての子どものその人らしい成長を支援する
6-2 障がいに関する関係法規をチェックしよう
6-3 適切な案内のために
サービスを体系化しておさえる
6-4 児童福祉法に基づく障がい児支援サービス
6-5 自治体が行う事業管理と利用に関する事務
COLUMN 6 一人ひとりの教育的ニーズを踏まえた学びの充実
第7章 子育て家庭への経済的支援・ひとり親家庭支援
7-1 安定した生活による子ども・家庭の福祉向上
7-2 手当支給の業務
7-3 福祉医療費助成の業務
7-4 業務をスムーズに進める
税・公的医療保険・年金の基本
7-5 ひとり親家庭支援の意義と読んでおくべ
内容説明
支援の基本、相談対応、多職種連携。実務の要点を完全網羅!支援をつなぐ、育ちを支える。エッセンシャルワーカーの仕事の全てがここに!
目次
第1章 子ども・子育て支援部門へようこそ
第2章 担当者が心得るべき仕事の初手
第3章 母子保健
第4章 家庭での子育てと子ども育成支援
第5章 幼児教育・保育
第6章 障がいのある子どもへの支援
第7章 子育て家庭への経済的支援・ひとり親家庭支援
第8章 社会課題のしわ寄せを受ける子どもへの支援
第9章 仕事を深める次の手
著者等紹介
水畑明彦[ミズハタアキヒコ]
1977年神戸市生まれ。2004年神戸市入庁。市役所、区役所、福祉事務所及び教育委員会事務局で、子育て支援や学校教育、幼稚園の再編、障害者の相談支援、住民総合窓口などを担当するなかで、神戸市における子ども・子育て支援の新制度構築や、教育振興基本計画の策定に従事。保育士、社会福祉主事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。