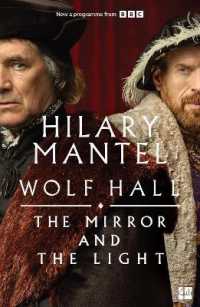出版社内容情報
★【特別セール開催中!】ご注文はこちらから
内容はこちらからご覧いただけます。
本書の特色
・草木による天然染料で忠実に再現
「紅百回茜百回」といわれるほど、自然の植物からの染色法は美しく仕上げるために何回も染めるので時間がかかる。また、染める季節は気温の低い冬に限られるため、本書の染め上げにも六年の歳月がかかっている。それだけに化学染料、顔料ではとうてい再現できない美しいものとなる。
・正絹の染布で作った初の日本色彩見本帖
江戸の紺染一枚のみ木綿を使ったが、あとの一三九四枚は、最も発色の良い正絹羽二重に染めた。文献に残された色名だけでも九○○余色あるといわれる日本の色彩の実物色見本帖は初めてのものである。技術的に困難な染布貼付の製本技術も新しい方式を採用した。
・染色法の過程を分析提示した
一つの材料から一つの色を染めるだけでなく、先人はさまざまな交染を工夫し複雑な色を作りあげている。その過程を染布で示した。また、染色の文献が正しいかどうかを批判しつつ、ある色を特定しなくてはならない。その試行錯誤からたった一枚の色を得るために何日もかかることが珍しくない。染めの分析過程で、分量、媒染の間違いを発見したものは、本書で初めて提示した。
・古代から江戸まで歴史的に編集
現代でも新しい色が生まれるように、色彩は時代の美意識と価値観を反映して作られ、色名も変化していく。従来、日本の色彩を概観する場合、時代を無視してひとまとめに並列させているが、本書は色彩の登場を歴史的に追う視点を重視し、色を個別のものとしてではなく文化史の中に位置付けようとした。
・古典文学、歴史理解に必携
『源氏物語』『枕草子』等の平安文学から江戸の文学まで。あらゆる古典に色名は登場するが、それがどんな色であるかの確認は専門家でもできにくい。本書は、その当時の色彩の再現を果たす事によって、一目で色名、配色が理解でき、最もわかりにくい、平安時代の「襲色目」「重色目」も、初めて多くの例を実物の布色で再現した研究者必携の書である。
・日本色彩史と染色技術の詳細な解説書付
別巻として、古代から江戸までの本編に収録した色彩、配色の研究の成果をまとめ、色彩が各時代の美意識の現れからとの考えから、何ゆえこの色、配色が生まれたかという歴史的変遷、またその染色の技術を個々の色にわたって開示し、著者独自の説を収録した。
日本色彩美の歴史
・階級で分けられた古代の色
飛鳥、奈良時代の日本は、鮮やかな原色を中心とした中国文化の影響下にあり、染色法も木や草の汁を直接布に摺り込む原始的手法から、「漢方薬」の煎じ液に浸すことに始まった「浸(しん)染(せん)法」という大陸の技術を使うようになった。基本色は、陰陽五行説に基づいた「五方正色」と「五方間色」であり、間色をいやむ色としていた。こうした色彩は、正倉院宝物、法隆寺献納物等によって知ることができる。聖徳太子は、五方正色に紫を加え、階級によって冠と衣服に使用する色をきめた(冠位十二階の制)。この制度は、孝徳天皇の時代に緑を加えた七色十三階に、持統天皇の時に庶民の色を黄と黒に決めるといったように、時代と共に複雑に変化していく。
・配色の独創を競った平安時代の色
宮廷貴族たちは、制度として決められた色彩のほかに、日常生活の中で四季折々の自然の色を取り入れた彩度の高い中間色と数多くの配色を生み出していった。日本独自の色彩美が花開いたのはこの時代であり、これを一般に「王朝の色彩」と呼んでいる。男性の衣服における配色を「重色目(かさねのいろめ)」といい、女性の衣裳の配色を「襲色目(かさねのいろめ)」(襲の字は、前のものに沿って重ねる意)という。その配色には、それぞれ「莟紅梅(つぼみこうばい)」「桔梗(ききよう)」といった名前がつけられ、特に、女性の十二単(じゆうにひとえ)の多色配色には、「山吹(やまぶき)の匂(におい)」「紅紅葉(くれないもみじ)」といった自然から着想を得た美しい名がつけられている。配色に名稱をつけて優雅を競った文化は、日本独自のものである。
【重色目(かさねのいろめ)】
男性の日常服の表地と裏地の配色をいう。例えば「藤重」と名づけられた配色は、表に薄紫、裏に萌黄を配し、その二色が透けたり見え隠れする風情を美しいとしたものである。春夏秋冬それぞれに季節の草花を模した配色を何十種類も創りあげ季節ごとに着た。合色目(あわせのいろめ)ともいう。色目とは色の名目(呼び方)の事。
【襲色目(かさねのいろめ)】
平安女性の晴装束である十二単は、たくさんの袿(うちき)を重ね着し、一番下に単(ひとえ)を着るのをいう。多いのは二十一枚も着たようだが、後には五(いつ)つ衣(ぎ)、つまり五枚重ねが普通となった。この五枚の裏表十色に単を加えた色の 袖口、裾に現われた多色配色を襲色目という。この配色法にも、女性が文に使う染紙の薄様を模した「薄様(うすよう)」や、グラデーションを使った「匂(におい)」等、高度な工夫がなされ、いずれも季節にちなんだ草花の風情を命名した。
・世界に類のない江戸の色
日本の色彩に対する感覚は、鎌倉以降、武家社会に入ってから無彩色に色を感じる「わび、さび」の美意識に代わっていく。やがて江戸の町衆は、華美、奢侈を否定する武家の支配の下で、まったく新たな色を創り出す。鮮やかな自然の飽和色を遊び競った王朝に対して、くすみのある不飽和色を主流に、複雑な染色技術を駆使して、「粋」の美意識を競った。色名も「利休鼠」「路考茶」といった有名人や役者の名をとる遊びが生まれ、"四十八茶百鼠(ちやひやくねず)"、といわれるほどの微妙な色分けと色名を楽しむ。色がそれ自体で流行するという現象はこの時代からのものである。
【役者色・路考茶(ろこうちや)】
江戸時代には歌舞伎役者が好んだ色が流行色となった。路考茶は、二代目瀬川路考が着た小袖の色である。茶色という言葉は王朝の色名にはなく、江戸時代に鼠色と共に、「粋」の美と認められたものである。他に役者色といわれるものに、璃寛茶、岩井茶、梅幸茶、芝翫茶、桝花色等がある。
・日本色彩の材料と技法
自然の植物を染料にする場合、草、花、実、葉、木、根、樹皮と発色する材料はさまざまである。その煎じた汁に浸すだけで染まるものもあるが、媒染剤を用いることによって発色に多様な変化が生まれ、またかけ合わせによっても様々な色が生まれる。ここにこの染色法の色の奥深さがある。
【五方正色(ごほうせいしよく)と五方間色(ごほうかんしよく)】
中国では古くから、宇宙を「五行」(木火土金水)の気のめぐりとしてとらえる考え方をし、五行に方位と色を付与した。つまり、木は「青」、火は「赤」、土は「黄」、金は「白」、水は「黒」。これを五方正色といい、この中間色(緑(みどり)、碧(へき)、紅(こう)、紫(むらさき)、瑠黄(るおう))を五方間色という。
【冠位十二階(かんいじゆうにかい)の制(せい)】
陰陽五行の「仁・礼・信・義・智」に「徳」を加え、その大小で十二階とした。中国では間色にしている紫を「徳」に当てたのは、天、徳のごとく広大なりという考えから来ている。
また、五行は相剋の関係、つまり火(赤)は金(白)を、水(黒)は火を、土(黄)は水をそれぞれ剋す関係だといわれるので、どの色からも剋されない超越した当時の表徴であった紫を置いて、最高位としたものであろう。
第一巻
古代の色
第二巻
平安時代の色 重色目 四季
第三巻
平安時代の色 重色目 四季通用
第四巻
平安時代の色 襲色目 古代から中世の色概観
第五巻
江戸の色
著者紹介
松本宗久
昭和元年京都で生まれる。昭和一九年、日本美術学校卒業と同時に学徒兵として中国へ。復員後、泥谷文景について水墨画を研修。和田三造(色彩による文化功労者)と知り会い、日本の色彩美(不飽和色)の研究をはじめる。昭和二六年、京都に戻り色彩の研究を開始。昭和三七年、文化庁文化財保護委員会の委嘱により、国宝等の修理とその指導を担当。昭和四九年、『草根花木皮染』(求龍堂)を刊行。昭和五一年より文化庁文化財課の依頼により、歴世服装美術復元制作、昭和五七年、『王朝盛飾』(学習研究社)刊行。
-

- 電子書籍
- 歌舞伎町ダブルオー SとSのバディ 分…
-

- 電子書籍
- ヤング宣言 Vol.2 ヤング宣言