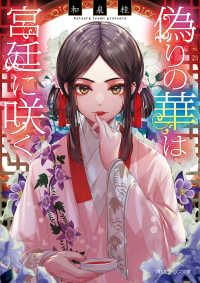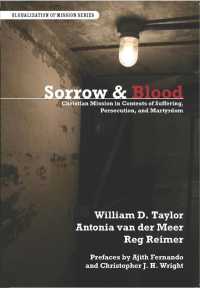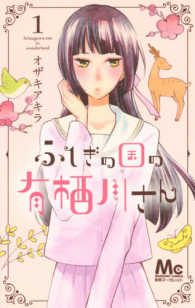内容説明
教科書よりもわかりやすい中東の大国イランの歩み。イランって、かなり複雑。なぜ、王朝の興亡がくり返されたのか?コラム「そのころ、日本では?」でグローバルな感覚も身につく!
目次
1 イランのはじまり
2 パルティアの時代
3 ササン朝ペルシア帝国
4 イスラム化するイラン
5 イラン人とトルコ人とモンゴル人
6 サファヴィー朝
7 ガージャール朝
8 ふたたび宗教国家へ
著者等紹介
関眞興[セキシンコウ]
1944年、三重県生まれ。東京大学文学部卒業後、駿台予備学校世界史科講師を経て著述家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まえぞう
27
23冊目はイランです。イランって、中東と中央アジア、ロシアとインドの交差点みたいなとこにあって、王朝の盛衰が面倒です。今のアラブ世界における立ち位置も独特ですし、これは一冊ではわかりませんね。2024/12/01
マカロニ マカロン
17
個人の感想です:B+。『テヘランでロリータを読む』読書会用。同書を読み解くにはイラン(ペルシャ)の歴史を知る必要があると感じ読んだが、本書はBCE4千年頃のメソポタミア文明とエラム人(イラン高原に居住)から、2024年のイスラエルとの戦闘に至る6千年の歴史なので、読み応えある。中には世界史の教科書でお馴染みのダレイオス1世、アテネとスパルタとのペルシャ戦争、ローマ帝国との戦争、ササン朝ときてようやくCE610年にイスラム教が創始。その頃日本では厩戸王が十七条憲法を制定。イランは先進国で、日本は開発途上国2025/09/18
ジュンジュン
13
「西洋と東洋の中間に位置し、東西の民族が行き来して文化が交わり、数多くの王朝が興亡を繰り返した(はじめに)為だろう、全編通じて王朝交代劇が続く目まぐるしい展開。最初は大丈夫。ペルシア帝国などはギリシャとかの関係で有名だ。イスラーム後もアッバース朝まではなんとか。ただ、その先はしんどい。最後にホメイニが出てきてホッとする(笑)。2026/01/30
蕎麦
6
様々な国や人物の歴史でたびたび登場するイランについて知識を得たく手にとった。日本人としては、周囲を他国に囲まれている状況、特に常に侵略の気配を見せる遊牧騎馬民族に隣接している社会を具体的にイメージするのが難しい。王朝の入れ替わりが激しく、どこに国家的・民族的アイデンティティを抱けるのかわからない。その点で、イスラム教の果たす役割は大きいのだろう。近代以降の変遷が怒涛すぎて理解が難しい。2025/08/17
つっきーよ
4
アケメネス朝ペルシア、セレウコス朝シリア、ササン朝ペルシアなど古代から大国として活躍しイスラム化してからもウマイヤ朝、アッバース朝など存在感を維持する。アラブ人、トルコ人、モンゴル人など支配者が変化するがイラン人は一貫して官僚として政治中枢に身を置く。19世紀にはロシアやイギリスなどの侵略を受け近代化することで対抗しようとするもうまくいかない。列強の植民地のような扱いを受けるが第二次世界大戦を機会に独立。石油の国有化により軍事大国に。革命が起きレザー・シャーをアメリカがかくまったことで反米意識が強まる2025/04/22
-
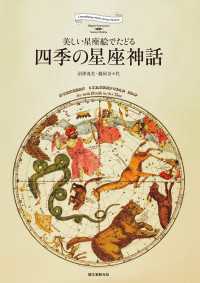
- 電子書籍
- 四季の星座神話 - 美しい星座絵でたどる