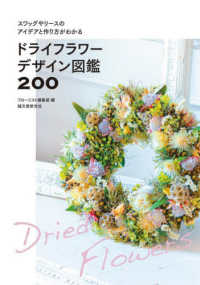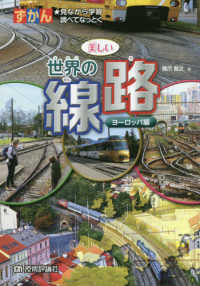内容説明
いいなづけのルチーアと別れ、一人ミラーノに着いたレンツォは、パン暴動に巻き込まれて、警察に追われる身となってしまう。一方、やっとのことで修道院に身を寄せたルチーアにも、さらに過酷な試練が待ち受ける―卓抜な描写力と絶妙な語り口で、時代の風俗、社会、人間を生き生きとよみがえらせ、小説を読む醍醐味を満喫させてくれる大河ロマン。
著者等紹介
マンゾーニ,アレッサンドロ[マンゾーニ,アレッサンドロ][Manzoni,Alessandro]
1785‐1873年。19世紀イタリア最大の国民作家。ミラーノの貴族出身。1827年発表の『いいなづけ』は、近代イタリア語の規範を作ったとされる。1860年上院議員となり、イタリア統一の精神的指導者として国民的尊敬を受けた
平川祐弘[ヒラカワスケヒロ]
1931年東京生まれ。東京大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
128
まだ中巻では、まとまる物もまとまらないだろうなと思っていたら案の定だ。レンツォがお尋ね者にまでなってしまうし、ルチーアはロドリーゴから隠れなければいけないし。さすがにイタリアだと思うのは、枢機卿や神父様など、たくさんの聖職者が出てくるところ。殺人者から改心して神父になったり、司祭失格と思われるアッポンディオを怒ったりするがそれで済むのかという呑気さがある。悪い奴らも、本当にやることが悪いのだが憎めないところもあり…。下巻では、やはりおさまるべきところにいくのかな。というのも、悲劇になりようがない気がする。2017/03/17
のっち♬
98
暴動に巻き込まれて警察に追われる身となったレンツォは従兄の元に身を隠す。攫われたルチーアは悪党の改心により領主に引き渡されずに解放される。誘拐に比べて改心や説教の場面に重心が置かれているのは一つのポイントだろう。その劇的な演出や人物造形には「時流にとらわれぬ美徳」を「もっと目のあたりに見たい」という著者の意見がくっきりと現れているようだ。しどろもどろ言い訳をして枢機卿に叱られる司祭のユーモラスな描写でコントラストをつけたりと独特のバランス感覚。善意が残っていれば断罪しないところに著者の包容力が現れている。2021/03/02
翔亀
37
【コロナ43-2】(上巻の続き)舞台は1628年のミラノ公爵領。スペイン支配下だ。スペインと独仏のマントヴァ継承戦争の戦場でもあり支配者の動向も描かれる歴史小説だが、物語の視点は一貫して農民=若い男女の結婚に至る文字通り波乱万丈の別離と逃亡と再会の物語だ。かつ、のどかな農村風景から大都市ミラノの暴動まで見事な描写で飽きさせない。また、心根卑しい悪役の領主も領主らしくふるまい、優柔不断の村の司祭はどうしようもない自己中心だが司祭らしくふるまう。両者とも描写はユーモアあふれ、完全否定はされない。一方の聖人↓2020/08/16
かごむし
29
客観的にみれば小さな物語なのだが、そこに人間が凝縮して詰まっている。普通だったら割り当てられるであろう役柄を登場人物たちは演じない。弱き善人はたやすく悪へと転じ、強き悪人は神の光の中で改心を誓う。狡い小人、気高き聖職者。どんな人物の中にも自分を見出してしまい、一体これは何を読まされているのだろうかと不思議な感覚に陥る。奇をてらうところのない、ごく当たり前な設定を、順調に進行していく。一直線の大道を歩むが如き小説だが、よほどの力量があるからこそ、読み物として、文学として成立しているのだと思う。訳もまた素敵。2018/05/15
ネロ
19
ここまで900ページ以上を読み進めたが次々現れる魅力的な登場人物とその心情を厚み多く語られる表現方法には舌を巻く。なのに主人公レンツォとルチーアが未だにどんなキャラクターなのかよく分からん笑。レンツォの印象に対し、ルチーアとその母アニューゼは「本当にいい人、おとなしい子でおとなし過ぎるような子」と評するがそんな者が群衆に向かって独演し扇動し警察から隙をついて逃げ出す様な大胆不敵ができるだろうか?ルチーアに至っては"この身が助かって母の元に帰れるならレンツォを諦めます"と神に願掛けしてしまう始末。うーん。2023/08/04
-
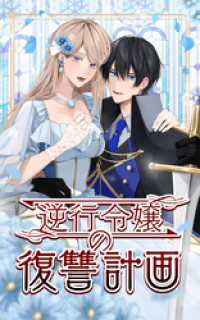
- 電子書籍
- 逆行令嬢の復讐計画 第32話【タテヨミ…
-

- 電子書籍
- ハンターのフィアンセとして生き抜く【タ…