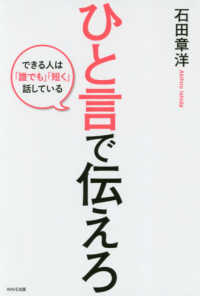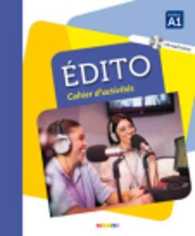出版社内容情報
【著者紹介】
1867年和歌山市生まれ。博物学、仏教学、自然科学等をもとに独自の方法論を確立した、博覧強記の民俗学者・粘菌学者。おもな著書に、『十二支考』『南方閑話』『南方随筆』『燕石考』など。1941年没。
内容説明
近代人類学に対抗し、独力で切り拓かれた「南方民俗学」。代表作「燕石考」などの論文と、ライバル柳田国男への書簡を中心に、現代の構造人類学の方法と思想を先取りし同時にその彼方をもめざした、具体の科学をまとめる。南方民俗学の方法は、私たちの時代に熊楠が残してくれた、信じられないほど豊かな世界を開く鍵である。
目次
第1部 具体の科学としての南方民俗学―論文集成(千里眼;平家蟹の話;山神オコゼ魚を好むということ;西暦九世紀の支那書に載せたるシンダレラ物語;猫一疋の力に憑って大富となりし人の話;人柱の話;邪視について;睡眠中に霊魂抜け出づとの迷信;通り魔の俗説;睡人および死人の魂入れ替わりし譚;臨死の病人の魂、寺に行く話;睡中の人を起こす法;魂空中に倒懸すること;ダイダラホウシの足跡;厠神;ひだる神;鷲石考;燕石考)
第2部 世界民俗学へ―柳田国男宛書簡より(オコゼについて;山男について、神社合祀反対の開始、その他;粘菌の神秘について;言語の音、幼児の言語獲得について、その他;無鳥郷の伏翼、日本人の世界研究者、その他;狂人になること、反進化論、その他;剃頭した親子、盛長する石、その他;神社合祀反対運動の終結、その他;ルーラル・エコノミーについて、柳田批判、その他;猥雑の肯定、その他;民俗学雑話、山男についての結論、その他)
著者等紹介
南方熊楠[ミナカタクマグス]
1867‐1941年。和歌山生まれ。博物学者、生物学者、民俗学者。大学予備門中退後、米英に留学、大英博物館に籍を置く。帰国後、田辺で粘菌の採取研究や民俗学に力を注いだ。博覧強記の人として知られる
中沢新一[ナカザワシンイチ]
1950年、山梨県生まれ。明治大学野生の科学研究所所長。思想家、人類学者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
roughfractus02
記憶喪失した男
悠
-

- 電子書籍
- エモーショナルイヤイヤ期 ~人間を3年…
-
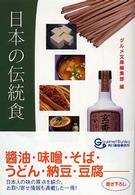
- 和書
- 日本の伝統食 グルメ文庫