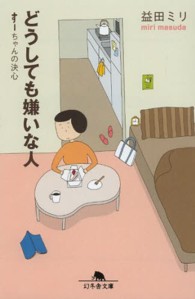内容説明
「イタリア文学論」ギンズブルグ、サバ、ウンガレッティ、そしてダンテなど、愛した作家や詩人たちの作品論を収録。イタリア文学への望みうる最良のガイド。「翻訳書あとがき」親しみ訳した作家たちの肖像、その魅力の核心が生き生きと紹介されている。
目次
イタリア文学論(ナタリア・ギンズブルグ論;イタリア中世詩論;イタリア現代詩論;文学史をめぐって)
翻訳書あとがき(『ある家族の会話』訳者あとがき;『ある家族の会話』新装版にあたって;『マンゾーニ家の人々』訳者あとがき;『モンテ・フェルモの丘の家』訳者あとがき ほか)
著者等紹介
須賀敦子[スガアツコ]
1929‐98年。兵庫県生まれ。聖心女子大学卒業。上智大学比較文化学部教授。1991年、『ミラノ 霧の風景』で女流文学賞、講談社エッセイ賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はっせー
62
全集修行も佳境になってきており、残り3巻で終わってしまう。もうすぐゴールだという喜びともう終わってしまうという悲しさの両方が押し寄せてきている。今回の6巻はイタリア文学の書評と訳者あとがきをまとめたものになっている。正直にいうと一番理解するのが難しかった気がする。イタリア文学の知識がなかったためかすんなり入ってこなかった。だがこれもこれで楽しもうと思ったため満足した!2023/10/11
かもめ通信
28
私にとってこの本の読みどころは、なんといってもナタリア・ギンズブルグ。2つの論考の読み応えといい、翻訳書あとがきといい、須賀さんがどれだけナタリア・ギンズブルグその人とその作品を愛していたかがよくわかる。『マンゾーニ家の人々』の日本語訳に、はなはだ懐疑的であったというナタリアが、須賀さんの説明を聞き、しばらく考え込んだ後、「あの本があなたの言うようだったら、わたしがこの作品を書いた目的が達せられているのだから、うれしい」とつぶやいたというくだりがとても好き。2020/05/08
no.ma
9
全集というのは須賀さんが翻訳した本のあとがきまでまとめて読めるのがありがたい。あとがきにも須賀さんの魅力があふれていた。ナタリア・ギンズブルグとアントニオ・タブッキに須賀さんの文章の秘密があるのだなと思った。2018/01/01
コニコ@共楽
7
須賀さんの全集も6巻目。全集を通して、落ち着いた静謐な佇まいの表紙に惹きつけられるが、特にこの6巻の「モランディのアトリエ」がいい。近代イタリア美術史に最も重視されたモランディを表紙にもってきた編者のセンスの良さも好感が持てる。須賀さんのイタリア文学論も彼女がイタリア文学史の中で最も重要だと考えている数々が明晰に語られて、敬服の一語に尽きる。紹介されている本を、呆れることに一冊も読んでいない私は、慌ててタブッキとギンズブルグを読み始めた。イタリア文学の最高峰「神曲」を読むのは、私の生涯の宿題。2012/09/27
やま
5
タブッキやギンズブルグなんて知らないよと思っていたが、この本を読むと捜して読んでみようかと思ってしまう。それほど魅力的なあとがき、また解説。そして、いつの時代のイタリアの事かという年代がその物語の背景を考えても大事であると言う当たり前のことに気づかされる。2014/07/08
-
![月が綺麗ですね[1話売り] story10-2 花とゆめコミックススペシャル](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1440520.jpg)
- 電子書籍
- 月が綺麗ですね[1話売り] story…
-
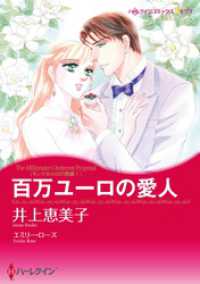
- 電子書籍
- 百万ユーロの愛人〈モンテカルロの誘惑Ⅰ…