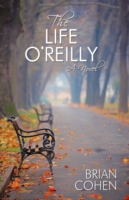内容説明
海の民、山の民、川の民、村の民、町の民。それぞれの職業との関わりとその変遷、またお互いの交流・交易のありようとその移り変わりの実態を、文献渉猟、徹底したフィールド調査、そして刻明な記憶をまじえながら解明していく、生業の民俗学の決定版。差別・被差別の民俗学とも深く結び着いてゆく。
目次
序 現代の職業観(きらわれる農業;女の本音;労働者意識;新旧の職業;肩書)
第1章 くらしのたて方(自給社会;交易社会;職業貴賤観の芽生え;海に生きる;山に生きる;旅のにない手)
第2章 職業の起り(村の職業;流浪の民;振売と流し職;身売から出稼へ)
第3章 都会と職業(手職;市と店;職業訓練;古風と新風;町に集る人々)
著者等紹介
宮本常一[ミヤモトツネイチ]
1907年、山口県周防大島生まれ。民俗学者。天王寺師範学校卒。武蔵野美術大学教授。文学博士。徹底したフィールドワークと分析による、生活の実態に密着した研究ぶりは「宮本民俗学」と称される領域を開拓した。1981年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
122
海。山、革、村、町。それぞれの民の職業について。現在も受け継がれている仕事もあれば、ほとんど絶えてしまった職業もある。時代劇にでてくる商いを営んでいる店の丁稚についても書かれており興味深く読むことができた。そういえば私の子供の頃の事を思い出してみると、町角でヤカンや鍋を修理する鋳掛屋や、獅子舞、どこにでもあったタバコ屋にはお婆さんが店番していたし、風呂屋で使う木切れを運ぶトラック、リヤカーを引き歩くボロ買いetc。なんでも合理化や都市化に伴って消えてゆく。50年語はどんな仕事が無くなっているのかな。2021/12/03
Willie the Wildcat
74
海・川・山などの自然と生活の繋がり、都会と地方、職業の変遷など、陰陽両面での文化の振り返り。維新・大戦などの歴史的うねりとは無関係に築かれる貴賎観が印象的。特にその自然発生的な醸成に、「生」の本質の一端。掲載写真は、当時の風景及び”言葉”の理解にもれなく一助。中でも印象的なのが、『振売』の写真。情緒豊かで、”良さ”が滲み出てる。読後感じるのが、開国と共に花開いた多様性の一方で、植え付けられた”官尊民卑”の功罪。但し、それも踏まえた故の表題なんでしょうね。2018/11/05
きいち
35
冒頭、この時の農村へのネガティブな記述で始まることに驚く。◇自給できる村の世界。そこは豊かで、一人が何役もこなすため職業は分化しない。一方で別のムラは生産力が弱く交易に頼らねば生き延びられない。次三男を都市へ送り出し、変事があれば娘も売らねばならぬ。競争相手は多く特化し質を上げる必要がある、専門職はそうやって生まれた。あれ、これは日本企業の変化の記述か?グローバル化のこと!?◇最後まで読み、宮本が歴史をたどるのは冒頭の農村の苦境からの脱出方法を探るためとわかる。答えはない、あるのは模索し続ける宮本の姿だ。2018/01/19
Akihiro Nishio
21
相変わらず冴え冴えの宮本節である。前半は農村と、山の民、海の民の話で、宮本の得意な話である。後半は、流浪の民、行商民、出稼ぎ民、そして都市の職人にスポットをあて、自給経済の破綻から商工業の発展までの道のりを鮮やかに浮かびあがらせる。乞食と押し売りが紙一重であるとは宮本でなければ言えないだろう。元々自給できない北部の場所に、交換するための資源を得るために人が入り、それがやがて町として発展していく過程を、こうも見事に描写されると、先進国と途上国の立地についてより深く理解できる。こういう素晴らしい仕事をしたい。2018/04/23
Sakie
19
平地に定住して田畑を開き作物をつくる者(自給中心の村)と、食べるものを手に入れるためにものづくりなどにより交易をした者(自給が成り立たないため交易中心の村)を軸に、日本人が生きるために選択した生業の成り立ちを説く。田畑を拓き、村ができ、行商が訪れ、虹のもとに市が立ち、町ができ、門前に店ができる。それは現代、マルシェに珍しいもの欲しいものを探して回る私まで、15世紀初めから連綿と続いているのだ。日本は平地からすぐ山地だから、切り離してはどちらも成り立たないなど、すべて漏れなく書かんとする情報の量が凄まじい。2024/06/18
-
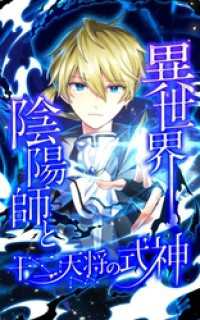
- 電子書籍
- 異世界陰陽師と十二天将の式神【タテヨミ…
-
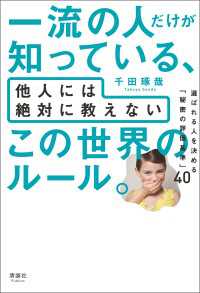
- 電子書籍
- 一流の人だけが知っている、他人には絶対…