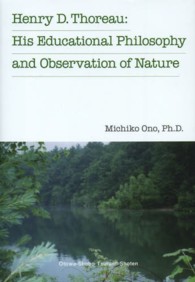内容説明
生誕100年をむかえる「最後の文士」吉田健一が遺した最後の長篇小説作品。無為な日々を送る主人公が友人たちと時に飲み、語らいながら、急激に変貌していく東京を彷徨う。「ただ生きていればいいのさ、」と、自分に対して自分を偽ることなく、自在にして豊穣な言葉の彼方に生と時代への冷徹な眼差しがさえわたる、比類なき魅力をたたえた吉田文学の到達点。高く評価されてきた名品をはじめて文庫化。
著者等紹介
吉田健一[ヨシダケンイチ]
1912‐1977(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kana0202
2
東京論として読める。途中まで。2022/11/26
渡邊利道
2
文庫版。解説が吉田健一の息女で特に新しい情報はなかった。「東京の今」という感じの最後の長篇小説だが、空白と充実がそのままのかたちで入れ替わる。ほとんどストア派的な抑制を感じさせる快楽主義は、「死ぬ時のように生きるのが生きることなんだよ」という認識に到達し、生まれたばかりですでに廃墟のような東京という町の中で「ただ生きる」ことを肯定する。独特のよるべなさとなげやりな倦怠を感じさせもする傑作とか名作とかではない忘れ難い作品。2018/03/05
ムチコ
2
――「又飼うのか、」と田口は言った。そして暫く黙っていてからそこにはいないかなり大きいと思われる犬の頭を撫でる手付きをした(本文より引用)。 主人公と季節折々の東京を歩き回る。うろうろした文体に「どこまで歩くんだろ」と思ってたのに、いつのまにか「もっと散歩していたいなー」と名残惜しくなっていた。わたしもそこにはいないかなり大きい東京の町を撫でた気持ち。 2016/03/08
のんき
1
「ただ生きていればいいのさ、」それが出来たらかっこいいなぁ。2012/06/20
gu
1
当たり前に考え、当たり前に生き、それを当たり前な文章で書いているのだろうと思う。傍目にはそれが難しいことに思えても。「併し唐松の注意はその見逃されるということよりも根本の方に行ってそれが例えばその家の木戸から玄関の明りに目を向けることだった。それだから正月の門松にも一つずつ輪飾りを付ける。又洋風の晩の食事に呼ばれて行って食卓で肘を張らないのは自分の両側に客がいるからである。そのように生きていることが多様であるのが唐松を喜ばせた」2012/05/25
-

- 電子書籍
- 精霊幻想記 15.勇者の狂想曲 HJ文庫
-

- 電子書籍
- あの日キミに2度恋をした。(フルカラー…