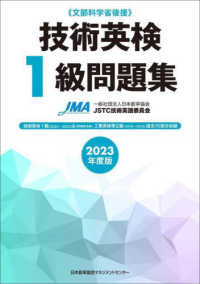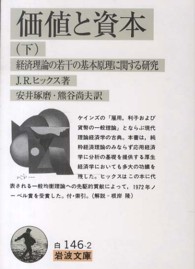内容説明
日本列島にあいついでやってきた諸民族の源流論と、先住諸民族を制圧しつつ成立したヤマト王朝の形成史という二つの論点を天皇制論義の基礎に置き、“日本単一民族”論の虚妄性の批判という今日的なテーマを実証的に展開する。日本民族の諸源流、天皇制、賤民、芸能史、部落問題を横断的に考察する、沖浦学の記念碑的著作。
目次
1 日本民族の諸源流(日本民族の五つの源流について―天孫族はどこからきたか;瀬戸内海の海賊衆―天皇の国家と海人;先住民族と近代文明―古モンゴロイド系のアニミズム思想)
2 天皇制と賤民制(天皇と賤民―両極のタブー;鎮護国家仏教の“貴・賤”観―インドのカースト制と日本の密教;仏教とヒンドゥー教―カースト制国家・ネパールを訪れて)
3 底辺に生きた人びと(日本文化の地下伏流―日本の芸能史における“聖”と“賤”;わが部落問題との出会い―被差別部落の古老と高橋貞樹)
4 天皇制の舞台裏(神聖天皇劇と民衆―明治維新の舞台裏;近世民衆文明の足跡―日本史の転換点;大帝の死―作家の日記より)
著者等紹介
沖浦和光[オキウラカズテル]
1927年、大阪生まれ。東京大学文学部卒業。比較文化論、社会思想史専攻。桃山学院大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ikuto Nagura
5
征服民が“貴”となり先住民が“賤”とされ、そこにヒンドゥーの教えが密教として入り込み、“浄”と“穢”のカーストで貴と賤を細分化していく。日本の国家形成過程で生み出され固定化された、神聖なる天皇と、賤しき下層民。本書は学術書でなく講演録や新聞への寄稿随筆であるが、旧体制の現代への遺恨を理解する上でとても勉強になった。部落出身の沖浦は、賤民が生み出した独自の文化が持つ美しさと力強さに誇りを持つ。大杉栄「美は乱調にあり」や徳富蘆花「新しいものは常に謀叛である」の名文を引く最終章は、現代への強烈なメッセージだな。2016/06/02
Junko Yamamoto
0
瀬戸内の島々に多数の被差別部落があることや密教がヒンドゥー教の差別感に基づいており空海もその意識を持っていたなど、面白い視点を得られた。しかし概して著者の差別への憤りが征服者が被征服者を虐げるという単純な見立てになっていることはエッセイだとして許容した。2020/09/17
-

- 和書
- 水力学 - 大学講義