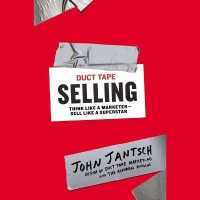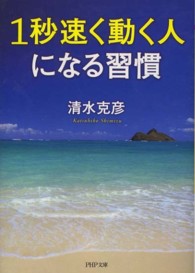- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 教育問題
- > いじめ・非行・不登校・引きこもり
内容説明
不登校の原因はさまざまですが、中でも発達障害のある子どもたちは友だち付き合いや学校の学習環境に対応することが難しく、不登校になるリスクが高いといえます。不登校をきっかけに発達障害の診断を受けるケースもあります。本書は多くの臨床例を持つ発達障害専門医の宮尾益知先生が、子どもたち一人ひとりが生き生きと過ごすために、家庭でできる支援の方法をやさしく解説します。
目次
第1章 激増している不登校児童や不登校ってどんな状態?
第2章 発達障害のある子どもが不登校になるとき
第3章 子どもが「学校に行きたくない」と言い始めたら
第4章 不登校の子どもへの具体的な働きかけと解決法
第5章 発達障害って何でしょう?
第6章 発達障害の子どもの心理的サポート
第7章 不登校の子どもの「これから」の選択肢を考える
著者等紹介
宮尾益知[ミヤオマストモ]
東京都生まれ。徳島大学医学部卒業。東京大学医学部小児科、自治医科大学小児科学教室、ハーバード大学神経科、国立成育医療研究センターこころの診療部発達心理科などを経て、2014年にどんぐり発達クリニックを開院。専門は発達行動小児科学、小児精神神経学、神経生理学。発達障害の臨床経験が豊富(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とよぽん
53
不登校、登校渋り、私の周りでもそんなお子さんをもつ親御さんが苦しい思いをしている。かと思えば、「子ども市役所」なる団体を作って、学校に行きたくない子どもの気持ちをわかってほしい、居場所をつくってほしい、と活動している親子もいる。教育委員会などが設置している不登校児童生徒の学びの場もあるが、あまり人気がないのである。不登校の子どもには発達障害をかかえる子が多い。同年齢の子どもや先生との関係をつくれないとか、学校という環境自体になじめない子どももいる。医療と行政あるいはNPOなど民間団体との連携が必要だ。2025/08/30
はる熊猫
1
「どんなことがあれば学校を休まなかったか」「学校に戻りやすいと思う対応」などのデータがあったのが良かった。高校生以上の不登校のデータが無かったのが残念だ。2025/04/25
-
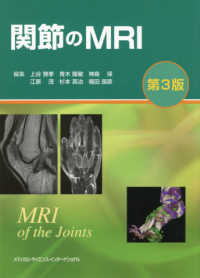
- 和書
- 関節のMRI (第3版)
-

- 洋書電子書籍
-
糖尿病テキスト(第5版)
Tex…