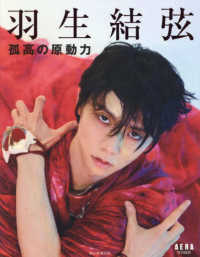内容説明
石は発展性・可能性こそが最も大切。比類なきスタイルで世界中の棋士、ファンから高い評価を受ける著者が、自らの碁の成り立ちや日本の碁などを自在に綴る。
目次
第1章 なぜ石が上に行くのか?
第2章 「日本の碁」を考える
第3章 棋士のセンスと人間性
第4章 碁は神様からの贈り物
第5章 これが宇宙流感覚
第6章 宇宙流の変遷
著者等紹介
武宮正樹[タケミヤマサキ]
1951年東京都出身。田中三七一七段に師事の後、64年入段決定、65年木谷実九段に入門。77年九段。76年本因坊となり、以降通算6期獲得。95年名人位につく。十段、世界選手権、などタイトル多数。2006年通算1000勝を達成。「宇宙流」とも呼ばれる棋風には世界中に多くのファンがいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
izw
1
碁はまともに打てないのですが、棋譜を見て並べながら、序盤、中盤の解説を聞いたり、読んだりするのは好きでした。ここ数年それもしていないのですが、武宮宇宙流の感覚的な解説が懐かしく、一気に読んでしまいました。とりあげられてい棋譜はざっと流して見ただけなので、こんど並べてじっくりと鑑賞したいと思います。2013/12/14
aesabu
1
自分の石を健康に、効率よく働かせる。攻められる不健康な状態をさける→石が上にいく→模様ができる→相手が入ってくる→封鎖し生きるのに手数をかけさせる2013/09/14
memoma
0
武宮九段の打つような独創的な碁は、石の形と模様に対しての天才的な感覚が必要であるとともに、相手の石を攻める力が必要不可欠だと思う。それらを併せ持った希有な棋士が世界的にも武宮九段ぐらいしかいないのであろう。ただし、石が上に向かわないような碁でも、効率を求めた結果としての勝敗は実力が同等であれば五分になるのも当然のこと。結局は棋風の話なので何がいいというものでもないのだけど、武宮九段の碁がたいへんに人をひきつけるのも納得できる。2013/12/08
kouki_0524
0
武宮さんが自身の宇宙流について語った本。打ち方にその人の人となりが出てくるというのは確かにそのとおりだと思ったし、それを受け入れる器の大きさが囲碁にはあると思う。だからこそ世界で親しまれているのだろう。2013/09/15
-
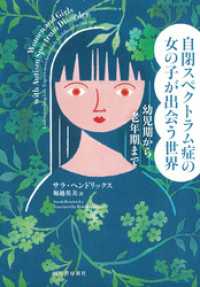
- 電子書籍
- 自閉スペクトラム症の女の子が出会う世界…