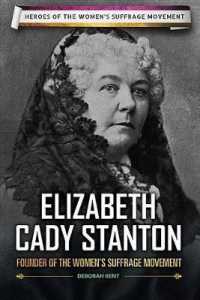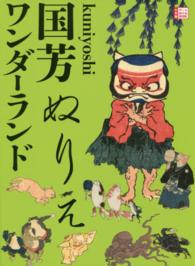出版社内容情報
ドゥルーズが美術を論じた唯一の書が新訳で復活。器官なき身体の画家としてのベーコンを論じながら、新たな哲学をつくりあげる名著。
【著者紹介】
1925年パリ生まれの哲学者。1995年、自ら死を選ぶ。スピノザやニーチェの研究を通じ西欧哲学の伝統を継承しつつその批判者となる。主著ーF・ガタリと共著『アンチ・オイディプス』『千のプラトー』『哲学とは何か』他。
内容説明
「ベーコンはいつも器官なき身体を、身体の強度的現実を描いてきた」「器官なき身体」の画家ベーコンの“図像”に迫りながら「ダイアグラム」と「力」においてドゥルーズの核心を開示する名著。ドゥルーズ唯一の絵画論にして最も重要な芸術論、新訳。
目次
円、舞台
古典絵画と具象との関係についての注釈
闘技
身体、肉そして精神、動物になること
要約的注釈:ベーコンのそれぞれの時期と様相
絵画と感覚
ヒステリー
力を描くこと
カップルと三枚組みの絵
注釈:三枚組みの絵とは何か
絵画、描く前…
図表
アナロジー
それぞれの画家が自分なりの方法で絵画史を要約する
ベーコンの横断
色彩についての注釈
目と手
1 ~ 1件/全1件
-

- 電子書籍
- 春日局(三) 光文社文庫
-
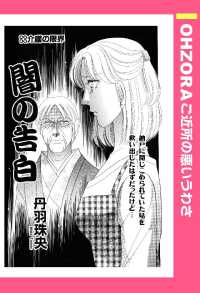
- 電子書籍
- 闇の告白 【単話売】 - 本編 OHZ…