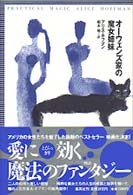内容説明
前巻における死と滅亡の徹底的な直視から、藝術と生の絶対的肯定へ。破滅の底の底からなおも響き渡る、俊傑・佐々木中の晴れやかなる朗唱。雑誌等未掲載対談・講演も収録。
目次
小説の言葉、思想の言葉―対談者:保坂和志×佐々木中
日本語ラップという不良音楽―対談者:磯部涼×佐々木中
この日々を歌い交わす
幾冊か選書、何のためでもなく
ところがどっこい旺盛だ。―対談者:古井由吉×佐々木中
敗北する歓び、敗北者たちの歌―対談者:宇多丸×佐々木中
「次の自由」へ向かう―対談者:坂口恭平×佐々木中
歓び、われわれが居ない世界の―“大学の夜”の記録
文学は死なず、革命は生き延びる
ニーチェを搾取し、ビジネス書を売りさばく今の出版界は死すべきか?
著者等紹介
佐々木中[ササキアタル]
1973年青森生。作家、哲学者。東京大学文学部思想文化学科卒業、東京大学大学院人文社会研究系基礎文化研究専攻宗教学宗教史学専門分野博士課程修了。博士(文学)。現在、法政大学非常勤講師。専攻は現代思想、理論宗教学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
32
対談集書評講演をまとめたもの第二弾。対談で著者の個人的な話がでてきて嫌々ながらに語るところがあり面白い。ラップ音楽を手がけていた時期があったとのこと。その縁でライムスター宇多丸などとの対談で日本のラップの歴史などを語り、知らない分野であるが興味深かった。古井由吉保坂和志などとの対もよかった。2015/05/28
寛生
27
【図書館】本書のタイトルと同じくするエッセイがこの本では読むに値するし、美しい。対談などでも、佐々木氏が読むこと、特に難解なものを読むことの重要性を繰り返し強調するのは理解できる。《読めないもの》を《読め》とする奨励。楽をしようとする読む者に警告を鳴らすのもいい。それならば彼にいってあげたい―こういう対談形式のものを活字にしないでください。それこそあなたが何か〈楽なもの〉を求めてくるからではないか?威勢はいい、言いたいことも伝わってはくるが、斬新な思想や哲学、新たな問題がここで提起されているわけではない。2014/01/09
多聞
7
アナレクタシリーズの第二弾。対談や講演、インタビューでの発言が主体。文学は勿論のこと、あらゆる芸術へや生の肯定をひたすら煽るアジテーターとも言える姿勢は相変わらず軸がぶれていない。佐々木中のバックボーンの一つであるヒップホップへの言及やブックガイドもあり、興味深い一冊だった。2012/01/15
白義
6
佐々木中のファースト対談集。思いの外ヒップホップ関連が多い。というかむしろ、感性的には佐々木中は硬派なヒップホッパーなんだろう。言葉のリズム、快楽を賞揚して読者を文学に煽るノリは変わらず、ただ対談集だから即興感がある。ブックガイドもついているのは有益。なかなかファンキーな本だ2011/12/16
UCD
3
再読。ニーチェとキリスト教を対立したものとして語ることで、どちらもダメにしてしまっているのではないか?そんな風に思う。佐々木中はその著書の中でどちらも救っているが、この本の「歓び、われわれが居ない世界の」ではニーチェが救われている。ニーチェはすべてに意味がないと言った。確かに言った。「神は死んだ」と。しかしそれだけではない。「新しい道徳、新しい法、新しい根拠、新しい理性、新しい意味を創りだすことです。それが本当に創造的で、根底的で、根源的なことである。ニーチェはそれを言ったのです」2013/11/27


![幼なじみがイケメンすぎる[ばら売り] 第3話 花とゆめコミックススペシャル](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1059155.jpg)