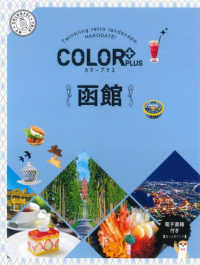出版社内容情報
文献のない縄文時代の言葉を確定できるのか。手掛かりは地名に。アオ、クシ、ミの三語とそれに派生する青、串、耳などの付く地名から縄文語を同定していく、実地調査に基づく論理的な試み。
著者情報
1944年生まれ。民俗研究家。 著書に『サンカの真実 三角寛の虚構』『葬儀の民俗学』『新・忘れられた日本人』『サンカの起源』『猿まわし 被差別の民俗学』など。
内容説明
アオ(青)、アワ(淡)、クシ(串、櫛)、ミ(三)、ミミ(耳)の五語は確実に縄文語であることを示し、それらから派生していく、キ(城、柵、木)、シマ(島)、岬、御崎、耳取、鳥居などの場所にまつわる言葉にさかのぼっていく、地名実証の研究調査紀行。
目次
第1章 青木、青島と縄文時代の葬地
第2章 弥生・古墳時代の葬地とアオ地名
第3章 青島を訪ねて
第4章 「クシ」の語には岬の意味がある
第5章 縄文時代に列島へ渡来した民族の言葉だった
第6章 クシと家船と蛋民
第7章 「耳」は、なぜ尊称とされていたか
第8章 ミ(御)の語源は数詞の「三」である
第9章 縄文語の輪郭
著者等紹介
筒井功[ツツイイサオ]
1944年、高知市生まれ。民俗研究者。元・共同通信社記者。第20回旅の文化賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
49
著者は元共同通信の記者で、現在は民俗研究者として著書も多い。以前『「青」の民俗学』という本で、地名をもとに縄文時代の言葉を探っていく方法を提示され、大変刺激を受けた。縄文時代に遡る文献がない以上、地名は縄文語を探る唯一の方法であるという著者は、地形地名ならば全国に散らばる現地に行き、自分の目で確かめるなど、大変篤実である。大湯環状列石の土版から、数詞の三と「御」を関連づけて考察したり、峠の語源を「手向け」とする説に対して、弓なりになった所を越えていく「タワ越え」であるとするなど、知的な面白さに満ちている。2023/04/06
nori
5
Gave up to read in half. I could understand why 青 as tomb places is related to 縄文語 with relatively small number of example. It may be related to understand how was 縄文時代 which might be different society from 弥生時代. 2023/03/31
Funky-TakaOyaji
1
文字が残っていない(存在しなかった)縄文時代の我々祖先は一体どの様な言葉・単語を使ってコミュニケーションを図っていたのであろうか。著者は地名にその痕跡が残っているのではないかと推測し、全国各地の地名を丹念に調べ、そこに共通する概念を見つけようと試みた。そして、アオは葬送、クシは岬、ミミは聖なる場所等其々が意味している事にまず気付き、注意深く証明をしていく。歴史学や考古学、言語学者等の専門家には考えつかないユニークなアプローチはとても興味深い。面白かった。2025/10/28
Kouhei Higuchi
1
古代の言葉を地名から推測する、その手法の奥深さ、楽しさはある。タイトルの通り縄文語であるかどうかを探求する本としては価値がある。そうかどうか確定は望めない。身近な地名をあらためて見つめ直すきっかけとなる。2023/05/11
-
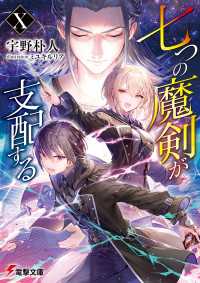
- 電子書籍
- 七つの魔剣が支配するX 電撃文庫
-

- 電子書籍
- バイタルサインからの臨床診断 改訂版 …