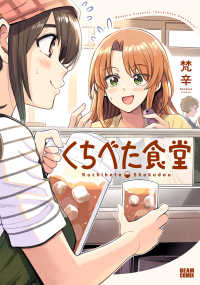- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
出版社内容情報
東北地方におけるアイヌ語地名の南限を厳密に見極め、大陸からやってきた人がそこでどのように交わり、民族が形成されたかを探る。
内容説明
アイヌ語地名の南限はどこか!?地名の安易なアイヌ語語源説を否定し、アイヌが暮らした東北のアイヌ語地名の南限を、「ナイ」と「ペッ」を中心に、科学的・実証的に地形などから策定する。そこから、アイヌと縄文人、蝦夷、マタギとの関連をみきわめ、“日本列島人”がどこから来たかを追求する。
目次
アイヌ語地名の特徴と癖
ホロナイ紀行
オサナイとサンナイ
トチナイ・アイナイ・ウラシナイ・ヨナイ
そのほかの「ナイ」地名
東北地方の「ペッ」地名
アイヌ語地名の南限はどこか
東側では複雑に入り組んでいる
異種言語による地名解釈
マタギはアイヌ語地名帯の狩人であった
マタギとの歴史と生態
「蝦夷」とアイヌは同じではない
アイヌと沖縄人は全く別の集団である
列島北部の先史時代
アイヌ語チメイノ南限界線は何を意味するか
著者等紹介
筒井功[ツツイイサオ]
1944年、高知市生まれ。民俗研究者。元・共同通信社記者。正史に登場しない非定住民の生態や民俗の調査・取材を続けている。第20回旅の文化賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
AICHAN
41
図書館本。厳密な検証により、アイヌ語地名の南限は西は秋田・山形の県境、東は宮城の石巻あたりと指摘。アイヌ民族と琉球民族は大陸では同じ古モンゴロイドだったが、列島に入ってからは一度も接触しなかったとも。となると、弥生人の流入により縄文人が北と南に追いやられ、北ではアイヌ民族となり、南では琉球民族になったという私の考えが成り立たなくなる。その考えを見直す必要がありそうだと思った。アイヌ民族はサハリン経由で北から列島にやってきて、琉球民族は別のルートで沖縄にやってきたのかもしれない。2021/03/27
活字の旅遊人
19
カバー写真に惹かれて購入。北東北の地名に北海道風のものがあり、それがアイヌ語由来だといわれれば、そうなのだと思う。地名のつけ方、残り方は多分いろいろある。そこに住んでいた者のことばが残る場合もあれば、後の支配者が名付けたものだったり、通りがかりの誰かが記録したものだったり。文字に残したもの勝ちなのは、否めない。おそらくそういった様々な経緯により、残っていた名前も更に変えられる。場所が近ければ、区別の為に敢えて変えるかもしれない。そういうところを考えずに、地名から民族移動を語るのは、早計な気もする。2021/01/24
perLod(ピリオド)🇷🇺🇨🇳🇮🇷🇵🇸🇾🇪🇱🇧🇨🇺
7
2017年刊。著者は元共同通信記者で在野の民俗研究家。 はじめに。日本各地の地名をアイヌ語で解釈する手法の安易さを批判し、4つの条件をつける。1.北海道と本土にそれぞれ同じかほぼ同じ地名が数箇所存在する。2.日本語はまず解釈がつかない。3.逆にアイヌ語だと容易に意味がつかめる。4.その地名が着いた場所の地形や特徴がアイヌ語の意味と合致する。確かに安易な解釈と思われる説は見た事があったので一定の条件が必要なのは理解できる。→2024/05/15
(k・o・n)b
6
著者は自称「アマチュアの地名観察者」。元記者なだけあり、取材力と行動力が凄まじい。アイヌ語由来と思しき地名があれば現地に赴き、地形を確認し、土地の古老に話を聞き、その上で文章を書いているので、読み応えがある。以前読んだ瀬川拓郎『アイヌと縄文』とは異なりアイヌと縄文人を必ずしも同一視せず、アイヌ語地名の分布域(=アイヌの居住域)の南限を比較的北の方に想定している。この地名分析の成果を背景に、後半は日本列島人の起源に話が及ぶ。この辺りは推測が多く、やや歯切れが悪いが…。全体的に読み物として面白かったのは確か。2020/01/31
相馬
6
民族研究者筒井さんの新刊はアイヌ地名と日本列島人の話。筒井さんの素晴らしいところは徹底した現地調査に基づくところ。地名の強権付会なこじつけではなく、実際に地形を調べ古老に聴き取りして考察しいる。そのためアイヌ民族の居住地をやや狭く厳密に捉えている。瀬川拓郎氏への疑問は自分も感じたところ。また、古墳寒冷期に人口減少した東北北部に北海道から南下した説は面白い。2018/02/11
-

- 和書
- 当世私本つれづれ草