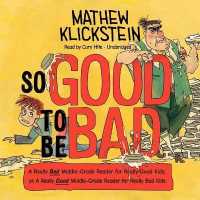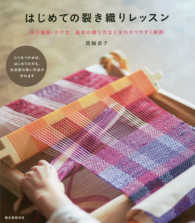出版社内容情報
最も早い時期に書かれた差別と被差別の問題・歴史を究明しようとした活気の書を、斯界の第一人者が現代語訳で甦らせる。
柳瀬 勁介[ヤナセ ケイスケ]
1868年生まれ。差別問題研究者。1896年、台湾で客死。
塩見 鮮一郎[シオミ センイチロウ]
1938年岡山県生まれ。作家。河出書房新社編集部を経て著述業に。主な著書に『浅草弾左衛門』『車善七』『江戸東京を歩く 宿場』『弾左衛門の謎』『異形にされた人たち』『乞胸 江戸の辻芸人』『吉原という異界』等。
内容説明
被差別部落の歴史を初めて書いた歴史的名著をついに現代語訳で!肉食のタブーは、日本中にケガレ意識を蔓延させ、皮革生産に携わる人、埋葬にかかわる人、刑の執行とその後片付けをする人びとを貶め、差別した。かような日本史をつらぬく「賎民意識の構造」を初めて鮮明に描いた、今もっとも読まれるべき伝説の書を、研究の第一人者が現代のことばで甦らせる!
目次
第1章 「えた」の名称(「えた」という名称の意義;「えた」の異名)
第2章 「えた」の起源(総説;餌取;外国渡来の民;内国の俘虜;落魄者;犯罪;雑種)
第3章 「えた」の状態(「えた」の地位;「えた」の風俗;「えた」の信仰と道徳;「えた」の人口と出生率)
第4章 「えた」排斥の原因(ケガレを忌む風習とその変遷;肉食の風習とその変遷)
第5章 救済策
著者等紹介
柳瀬勁介[ヤナセケイスケ]
1868年、福岡県直方市植木生まれ。17歳の折、隣村の小学校で教鞭を執る。東京法学院、日本法律学校で法律を学んだ後、前人未踏の「部落の歴史」の仕事にとりかかり、原稿を完成させた後にそこに書いた部落民救済策を実行に移そうと台湾に渡り、台湾総督府に勤める。当地で赤痢にかかり、その原稿を九州の同じ塾に学んだ友人権藤震二に託すが、刊行を見ずに1896年に病没した
塩見鮮一郎[シオミセンイチロウ]
1938年、岡山市生まれ。作家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ショア
今庄和恵@マチカドホケン室コネクトロン
イトノコ
乱読家 護る会支持!
メイロング
-
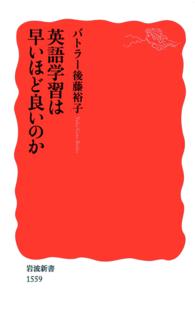
- 電子書籍
- 英語学習は早いほど良いのか 岩波新書
-

- 電子書籍
- どうしたら桜井さんのように「素」で生き…