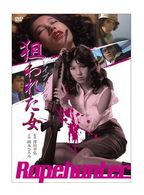出版社内容情報
白山神社はなぜ被差別部落に多いのか。北陸の地で時宗、一向宗にいかに駆逐されていったか、歴史的な推移からもその実体を追う。
【著者紹介】
1944年生まれ。元「新潮」編集長。『余多歩き 菊池山哉の人と学問』で読売文学賞受賞。
内容説明
ケガレから生まれ清まりへ。なぜ被差別部落に白山神社が多いのか?白山信仰がその一大中心地・北陸で、一向一揆に駆逐され、時宗との対立・融合をみながら、近世に入って蘇った姿を追う。民俗学永遠の謎に挑む、著者畢生のライフワークをまとめる述志の書。
目次
序章 白山信仰の謎と被差別
第1章 被差別部落が祀る白山神
第2章 悪所の白山信仰
第3章 神の子孫であることを主張する「河原巻物」
第4章 差別と暴力―菊池山哉の民俗世界にそって
第5章 白山信仰と柳田・折口
第6章 白山信仰と中世北陸の宗教風土
第7章 白山信仰と一向一揆
第8章 白山信仰と時宗系部落
著者等紹介
前田速夫[マエダハヤオ]
1944年、福井県生まれ。民俗研究者。東京大学文学部英米文学科卒業後、新潮社に入社、文芸編集者として雑誌『新潮』編集長などをつとめる。著書に『余多歩き 菊池山哉の人と学問』(晶文社、読売文学賞受賞)がある。「白山の会」会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
21
「白山の会」の各地の仲間と一緒に、現地踏査やらセミナーでの暴走やらしながら謎を追う後半三章の雰囲気、好きだなあと思って読み終わったら、あとがきでの、末期がんの中「とにかく今の研究成果をまとめてください!」という編集者の言葉に応えて急いでまとめたという告白にびっくり。あらためて、本当に学問っていいなあと思いました。◇調べてみたら、2013年のこの本以降、この人新しい本2冊も出したはるやん。素敵だ。◇金沢出張の晩、転勤してた友人と実現させた飲みの席で白山宮にお参りすることを話したら、薦められた本。ありがたい。2014/04/07
Yuusi Adachi
12
関西出身のせいか、被差別部落に並々ならぬ関心があります。小学校の頃はは川向うがまさにB地区でした。公立だったので、クラスにもいました。川の堰の向こうには山口組でも武闘派でおなじみの山健組の事務所と、先代山口組の渡辺組長の自宅が…お洒落な港町だけには収まらない神戸クォリティ。その地区には白山神社はなく、白山=被差別部落は東日本に多いように見受けられます。本書でも述べられているように、柳田國男説では、被差別部落民は現日本人です。私も同意見です。興味のない人には全く面白くありません。☆☆☆2014/03/05
田中峰和
7
白山信仰と被差別部落の関係について詳しく論じられる。「はくさん」ではなく「しらやま」と呼ばれる信仰はツングース系部族から朝鮮経由で泰氏によって到来した。土着のシラの信仰や仏教と集合して白山信仰が成立。金沢でも土着宗教として普及していた白山信仰は、浄土真宗に駆逐された。加賀の一向一揆など、武士からの搾取に抵抗した浄土真宗は、時宗や白山の信者を吸収して行く信者を拡大。秀吉や江戸幕府以前に、宗教的な迫害を受けた白山信者たちは被差別的処遇を受けた。非転向者として隠れ信者として差別されたという視点も面白い。2021/06/19
アメヲトコ
4
期待外れ。著者の問題意識と思いはわかるのですが、軸となる方法論を持たずに論を展開しているために話がちぐはぐで独りよがり、文体も不安定。さまざまなシンポやセミナーに顔を出しては議論を挑んだものの話が噛み合わなかったことをぼやいていますが、さもありなんという感じ。2016/10/01
芋煮うどん
2
興味深く読み進めたが咀嚼できたか、というと疑問。知識不足で後半ついていけていない。白山信仰と十一面観音のつながりは、意識したことがなかった。「水」ということのようだが。2024/08/16
-
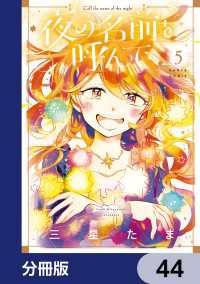
- 電子書籍
- 夜の名前を呼んで【分冊版】 44 HA…
-

- 電子書籍
- 千の星より、君だけが欲しい。 第46話…
-
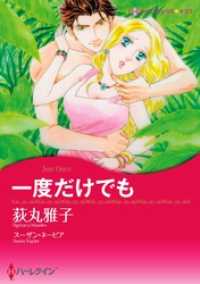
- 電子書籍
- 一度だけでも【分冊】 5巻 ハーレクイ…
-
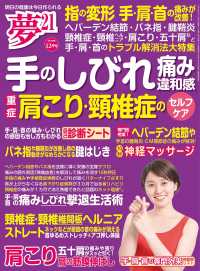
- 電子書籍
- 夢21 2019年12月号 WAKAS…