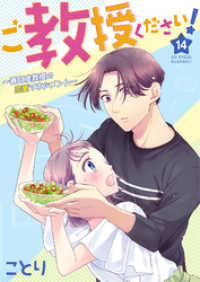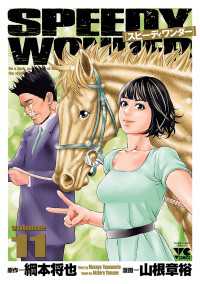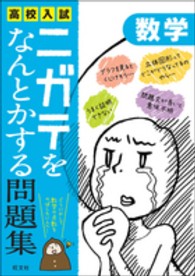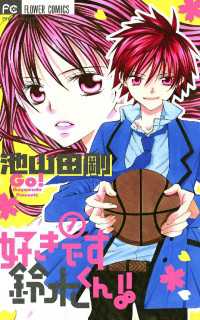出版社内容情報
明治神宮の建築文化的価値を解説する初の通史。
明治神宮鎮座百年祭記念出版。
近代にふさわしい神社はどうあるべきか――。
一見「復古」を志向しているようにみられる内苑の建築物にも、「国民国家」のもとに、日本の近代の特徴である「独自性」と「普遍性」を追求するという「日本近代を象徴する空間」が形成されていくさまを、未公開資料とともにひもとく。
近代につくられた神社の中で、明治神宮は、内苑だけでなく外苑が一緒に計画された点で、また皇族から政府高官・一般庶民に至るまで、世の中のあらゆる階層の人が参拝することを前提に計画された点で、特異である。
本書は、そこに、「独自性」(ナショナル・アイデンティティ)と「普遍性」(近代化)をともに追求するという、遅れて近代化をはじめた国特有のやり方が象徴的に示されていると見て、内苑と外苑の建築の計画経緯や設計趣旨について、明治神宮蔵の史料などをもとに明らかにしつつ、戦後復興社殿についても考察し、創立時の社殿を含め、「伝統表現」について多くの示唆が得られることを指摘している。
はじめに
第一章 明治神宮の創立
第一節 明治神宮内苑・外苑の現在/第二節 「明治神宮」内苑・外苑設置の要望/第三節 神社奉祀調査会での議論
第二章 内苑の建物
第一節 内苑計画の変遷/第二節 社殿の設計趣旨 ─ 秩序重視の空間構成と近代技術の活用/第三節 拝殿の使われ方/第四節 社務所に見られる特徴/第五節 旧御殿・隔雲亭・貴賓館
第三章 外苑の建物
第一節 奉賛会の献金募集/第二節 外苑計画の変遷/第三節 憲法記念館/第四節 陸上競技場/第五節 競技建設の追加/第六節 外苑周辺道路の整備/第七節 外苑計画にみられる特徴
第四章 宝物殿と聖徳記念絵画館
第一節 宝物殿の設計競技/第二節 宝物殿の建築史的価値/第三節 聖徳記念絵画館の設計競技/第四節 聖徳記念絵画館の建築史的価値
第五章 復興社殿の計画と設計趣旨
第一節 戦災と復興計画/第二節 復興準備奉賛会と造営委員会での議論/第三節 復興社殿の設計趣旨/第四節 貴賓館・参集殿・齋館・社務所、隔雲亭の建設/第五節 創立時と復興時の社殿にみられる設計姿勢の違い
第六章 日本近代を象徴する空間としての明治神宮内苑・外苑
第一節 明治神宮の近代性/第二節 独自性と普遍性の追求/第三章 伝統の継承ということ
あとがき
藤岡 洋保[フジオカ ヒロヤス]
著・文・その他
内容説明
近代につくられた神社の中で、明治神宮は、内苑だけでなく外苑が一緒に計画された点で、また皇族から政府高官・一般庶民に至るまで、世の中のあらゆる階層の人が参拝することを前提に計画された点で、特異である。本書は、そこに、「独自性」(ナショナル・アイデンティティ)と「普遍性」(近代化)をともに追求するという、遅れて近代化をはじめた国特有のやり方が象徴的に示されていると見て、内苑と外苑の建築の計画経緯や設計趣旨について、明治神宮蔵の史料などをもとに明らかにしつつ、戦後復興社殿についても考察し、創立時の社殿を含め、「伝統表現」について多くの示唆が得られることを指摘している。
目次
第1章 明治神宮の創立
第2章 内苑の建物
第3章 外苑の建物
第4章 宝物殿と聖徳記念絵画館
第5章 復興社殿の計画と設計趣旨
第6章 日本近代を象徴する空間としての明治神宮内苑・外苑
著者等紹介
藤岡洋保[フジオカヒロヤス]
1949年広島市生まれ。東京工業大学工学部建築学科1973年卒業、同大学院修士課程建築学専攻1975年修了、同博士課程建築学専攻1979年修了、工学博士。明治大学工学部助手(建築学科)などを経て、1984年東京工業大学工学部助教授(建築学科)、1996年同教授(建築学科)、2000年同大学院理工学研究科教授(建築学専攻)、2015年同大学定年退職、名誉教授。その間、神奈川大学、ワシントン大学大学院(シアトル)、明治大学大学院、北海道大学大学院で非常勤講師。2015~18年明治神宮特任研究員(非常勤)。日本近代のデザインや建築思想、建築技術、保存論などについて研究。2011年日本建築学会賞(論文)。2013年「建築と社会」賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。