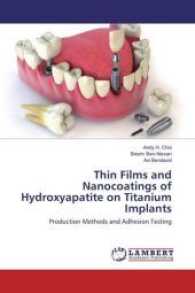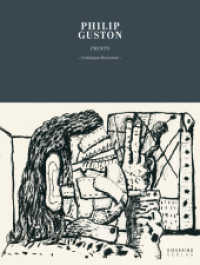内容説明
F・オットーは、吊屋根や大テントの構造建築の設計者として知られる。本書は、彼の思想をわかり易く解説しながら、多数の図版と写真を使ってビジュアルにまとめている。自然と技術との関係を理解するための恰好の入門書となろう。
目次
1 自然(生命のない自然;生きている自然;死んだ自然;動物たちの建築;自然と技術)
2 構造体(形―力―質量;硬いもの―柔らかいもの―非物質;硬い構造体;独立柱、支持柱、塔;梁―スラブ;分岐;アーチ、ドーム、シェル;柔らかい構造体;繊維、糸、ザイル、ネット、織布、皮膜;吊橋とザイル橋;吊屋根;テント;ニューマチック構造)
3 生きている構造体(嚢から技術へ;微粒子から生きた細胞へ;多細胞の有機体へ;生長;硬化をつく生長;硬い植物は柔らかく生長する;末端の生長;殻からの脱皮;硬化した単細胞;内骨格;骨の生長;発生のメカニズム;空間と時間の限界)
4 全体(自然に建てること;美的な存在;色彩;彩色された軽量構造体;住まい;太陽と影;愛と自然の建築に向けて)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
7
第二次大戦中ドイツ空軍兵士として都市の崩壊に衝撃を受けた著者は、大量生産と機能主義によって再興する都市建築に抗して巧みな構造計算から生み出される軽量建築を作り続けた。生物をモデルとした膜構造とテントをモデルとした吊り構造によって展開するその建築物は万博のパビリオン等で有名になり、ローマクラブの報告書『成長の限界』以後の脱工業社会における建築の方向を明確化する指標となった。「はじめに嚢ありき」と宣言する本書は、自然に対立せず自然に沿って自らを組織化する建築を、多数の図版とともに具体的に示す(1982刊)。2025/07/14
ymazda1
3
生物は、外力を自然に受け流せるように成長していくことで、後年流行った言葉を使えば、自己組織化してるってことでいいんかな? そして、これらの力学的な模倣したみたくにも感じられる、ケーブル構造や膜構造や逆懸垂構造?みたいなのが「自然な構造体」に近い構造で、接合点に大きな力が作用しようがお構いなしに直線部材を直角に組み合わせたラーメン構造みたいなのが、その対極の人工的な構造体って理解でいいんかな?