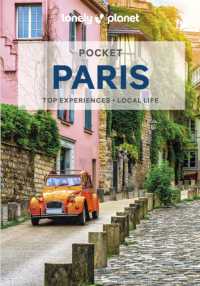感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
7
サンフランシスコの坂と江戸の坂の違いは、「中心」を重視する幾何学的グリッドが一方的に被さる設計と「奥」を重視する微地形に沿って軸線をずらしながら形成される設計にある、と著者はいう。江戸を例に日本の都市の構造を地形から検討し始める本書は、丘の起伏や微細な水系に沿った集落、信仰、流通の形成から都市の文化的ネットワーク図を素描する。ここから導出される空間はお屋敷型、町屋型、郊外住宅型、裏長屋型の4分類され、これら建築空間は自然に沿って形成されるゆえに抽象的中心はなく、自然の淵に消失する「奥」に触れているとする。2025/08/01
19番ホール
3
3章とくによかった2022/12/15
チャーリー
2
日本の空間は並行的な何重もの「仕切り」によって「奥」が生まれているちいうテーゼがさまざまな方向から語られている。グリッドパターンでも、西欧は絶対的な秩序を空間や地に投影しているのに対し、日本の場合は必要上、格子状になっているが地形や遠景の眺望によってしばしば歪められている。これは一神教対多神教や、大陸と島という単純な理由によるものではない。東南アジアなどは語られず、やや西欧に対する日本の独自性を過度に示しているきらいがないわけではないが、日本の地霊を具体的に考えていった一つの結果を明瞭に示している。2016/10/14
ネオジム坊
2
槇文彦は、戦後の日本を牽引した世界最後の建築運動「メタボリズム」の一角を担うが、その思想は菊竹や黒川のような分かりやすい『未来都市教』とは異なるように見える。彼は東西の聖域比較から、西洋の「塔=中心性」と日本の「境内=奥性」の構造を見出して、前者をデキリコの絵・後者を広重の絵に喩え論を結ぶ。しかし、対立項として論じられるべきはずの「西洋の奥性と日本の中心性」について本書では一切述べられていない。つまり、槇も他のメタボリスト同様「日本的なもの」を『輝かしい時代』のために「自作する」試みに加担したのであろう。2012/04/24
A
2
本書は日本、特に東京における都市の形態(表層)の背後にあって、常に表層において見えかくれしている都市の深層構造を「道」「奥」「微地形」「表層」などの観点から読み取ろうとした論文集。特に槇さんの「奥の思想」という論文は、自分が普段から無意識のうちに感じていたことがうまく言語化されていて感動した。欧州では、目に見える絶対的な「中心」性が志向されるのに対して、日本では、見えざる零度の原点としての「奥」性が志向されるというのはまさにという感じ。2011/06/10