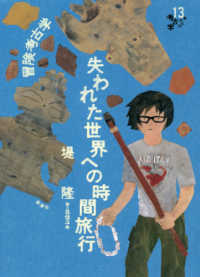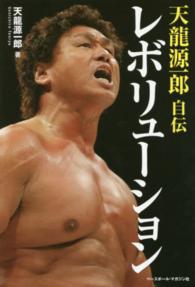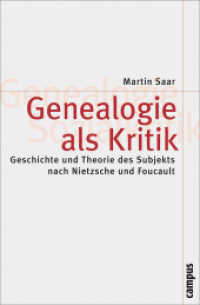出版社内容情報
近代建築を使いながら保存していくために、文化遺産としての価値を守りつつ、現代に適した性能をいかに付加するか。
何を変え、何を守るのか――。
近年、既存建物のリノベーションが注目を集めており、近現代建築の保存再生というテーマがより身近なものになってきているが、歴史と現代が調和した真に豊かな都市環境づくりには、まだほど遠い状況にある。既存建物の価値を十分に理解していないと思われる、奇妙な保存再生例が都市には溢れている。より多様な既存建物のリノベーションにおいても、優れた「保存再生デザイン」が求められているのである。(序論より)
内容説明
何を変え、何を守るのか。近代建築を使いながら保存していくために、文化遺産としての価値を守りつつ、現代に適した性能をいかに付加するか。
目次
序論 建築と都市の現在
1章 基本編―材料から考える(煉瓦造近代建築;鉄筋コンクリート造近代建築;木造近代建築 ほか)
2章 実践編―現代における課題(建築史研究と保存再生デザイン;文化財行政と保存再生デザイン;文化財構造物への構造補強の考え方とデザイン―文化財の耐震補強を知らずして、文化財の活用を語るなかれ)
3章 座談会―MonumentからLiving Heritageへ(オーセンティシティとインテグリティを考える;近代文化遺産における活用について考える)
著者等紹介
田原幸夫[タハラユキオ]
建築家/京都工芸繊維大学KYOTO Design Lab特任教授。1949年長野県生まれ。1973年京都大学工学部土木工学科卒業。1975年京都大学工学部建築学科卒業。1975年日本設計事務所(現・日本設計)入社。1984年ベルギー政府給費留学生としてルーヴァン・カトリック大学大学院留学。同大学院「歴史的都市と建築の保存修復センター」にてディプロマ取得。ユネスコ世界遺産「グラン・ベギナージュ」の保存活用設計に携わる。2007年5月‐2012年10月東京駅丸の内駅舎保存復原設計監理総括を経て、2014年4月より現職。日本イコモス賞、日本建築家協会賞、日本建築学会賞(業績)、日本建築士会連合会賞、BCS賞などを受賞
笠原一人[カサハラカズト]
京都工芸繊維大学デザイン・建築学系助教。1970年神戸市生まれ。1998年京都工芸繊維大学大学院博士課程修了。2010‐11年オランダ・デルフト工科大学客員研究員。DOCOMOMO Japan理事。住宅遺産トラスト関西理事。近代建築史、建築保存再生論専攻。日本建築学会賞(業績賞・共同受賞)、工学教育賞などを受賞
中山利恵[ナカヤマリエ]
京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科建築学専攻助教。金沢美術工芸大学美術工芸学部卒業。東京芸術大学大学院修士課程修了後、東京大学工学系研究科博士課程、有限会社金沢設計(降幡建築設計事務所金沢分室)勤務、公益社団法人金沢職人大学校修復専攻科を経て、2012年「日本の木造建築における『洗い』の歴史的研究―木肌処理技術からみた建築の経年に対する美意識の変遷」により博士(工学)学位取得。2015年12月より現職
石田潤一郎[イシダジュンイチロウ]
武庫川女子大学客員教授・京都工芸繊維大学名誉教授。1952年鹿児島市生まれ。1976年京都大学建築学科卒業。1981年同大学大学院博士課程修了。工学博士。京都大学助手、滋賀県立大学助教授、京都工芸繊維大学教授を経て2018年より現職。専攻は日本近代建築史。建築史学会賞、日本建築学会賞(論文)などを受賞
北河大次郎[キタガワダイジロウ]
(独)国立文化財機構東京文化財研究所室長。1969年静岡県生まれ。1992年東京大学工学部土木工学科卒業。1999年フランス国立土木学校博士課程修了。フランス国博士(国土整備・都市計画)。同年より、文化庁で主に近代化遺産の調査、指定等を担当。2010年から2年間イタリアの“31”ICCROM(文化財保存修復研究国際センター)でプロジェクトマネージャーを務める。2016年4月より現職。サントリー学芸賞、交通図書賞、土木学会論文奨励賞などを受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
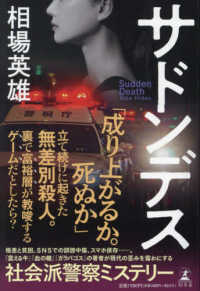
- 和書
- サドンデス