内容説明
鉄道橋に関する業務(維持管理・保全・更新)に携わる方々の参考になり、将来の橋梁技術発展に役立つことをモットーに、鋼鉄道橋に関する改革的技術の変遷と次世代に継承すべき経験的知恵をわかりやすく紹介・解説しています。
目次
鋼鉄道橋の改革的技術の概要と歴史
リベット橋梁から溶接橋梁への転換
ISO9000を先取りした鋼鉄道橋製作時の品質管理
設計の標準化の話―鋼鉄道橋の標準設計
景観を重視した上路トラス―中央本線新桂川橋梁
長大橋に列車を通す技術―緩衝桁・疲労設計
塗装しない鉄道橋(無塗装橋梁)の誕生―第三大川橋梁
新しい高耐候性鋼材を利用した新幹線橋梁―北陸新幹線:北陸道架道橋
鋼上路タイプとして普及した合成桁
新しい形式の複合橋梁―連続合成桁、CFT複合橋、合成トラス等〔ほか〕
著者等紹介
阿部英彦[アベヒデヒコ]
1931年東京に生まれる。1954年東京大学工学部土木工学科卒業・国鉄に入社。1956年国鉄・施設局特殊設計室(後の構造物設計事務所)に勤務。1959~61年国鉄よりアメリカ・イリノイ大学に留学、修士号を取得。1984年まで構造物設計事務所の主任技師、次長を経て所長(その間、2年間、鉄道技術研究所構造物研究室長勤務)。1984年国鉄を退社、宇都宮大学土木工学科教授に就任。1993年足利工業大学土木工学科教授に就任。鉄道用合成桁橋梁に関する研究で東京大学より工学博士を取得。土木学会・田中賞(論文賞、研究業績賞)を受賞
稲葉紀昭[イナバノリアキ]
1941年東京に生まれる。1963年日本大学理工学部土木工学科卒業。国鉄・日本鉄道公団の本社、地方機関に在籍。1983年国鉄構造物設計事務所次長(鋼及び合成構造)。1991年日本鉄道建設公団設計技術室長。2001年株式会社東京鐵骨橋梁専務取締役(技術本部長兼技術研究所長)。現在、株式会社東京鐵骨橋梁技術顧問・技師長、日本大学理工学部非常勤講師。鉄道用連続合成桁に関する研究で日本大学より工学博士を取得。特別上級技術者(土木学会)、技術士
中野昭郎[ナカノテルオ]
1933年東京に生まれる。1955年広島大学工学部土木工学科卒業・国鉄に入社。1959年国鉄構造物設計事務所。1974~76年都立大学工学部非常勤講師。1976年国鉄下関工事局技術管理課長。1979年国鉄構造物設計事務所主任技師。1985年前田設計株式会社(鉄道橋・道路橋の計画・設計)。1979~99年法政大学工学部非常勤講師。1999~2007年日本交通技術株式会社(海外鉄道橋の計画・設計)
市川篤司[イチカワアツシ]
1952年静岡に生まれる。1977年東京工業大学大学院総合理工学研究科修了・国鉄に入社。1980年国鉄構造物設計事務所。1987年財団法人鉄道総合技術研究所(線路構造研究室主任研究員、橋梁研究室室長)。1998年東京工業大学工学部土木工学科客員教授。2001年財団法人鉄道総合技術研究所(構造物技術研究部部長、研究開発推進室室長)。1997年東京工業大学より博士(工学)を取得。1997年、2003年土木学会・田中賞(論文賞)を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 憲法事件を歩く - 尊厳をかけて闘った…
-
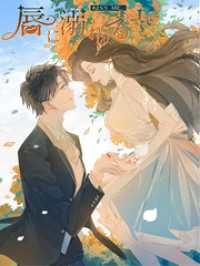
- 電子書籍
- 唇に溺れる 第6話 まさかの場所での再…
-
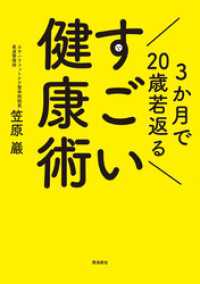
- 電子書籍
- 3か月で20歳若返るすごい健康術
-

- 電子書籍
- 新版 神経質の本態と療法 - 森田療法…
-
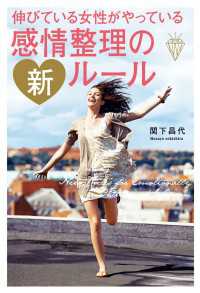
- 電子書籍
- 伸びている女性がやっている感情整理の新…



