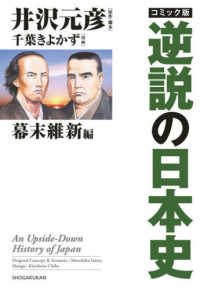出版社内容情報
故郷を喪失した「仮名書きの詩人」。蕪村ー江戸中期の俳人・画家。摂津に生まれる。別号、夜半亭など。享保の末頃江戸へ下り書画、漢詩、俳諧などを学んだ。画家としては日本文人画を大成。芭蕉・蕪村・一茶といった、江戸時代を代表する俳人のなかで享楽主義を内包し、もっとも近世的な俳人とも称される。おそらく、蕪村は生きていることがもたらす根源的な淋しさというものを、誰よりも鋭敏に甘受せずにはいられない人であった。
揖斐 高[イビ タカシ]
著・文・その他
内容説明
江戸を代表する俳諧の巨匠。芭蕉も及びえぬ境地を、画家としての眼が切り開いた鬼才の俳人。
目次
1 故郷喪失者の自画像
2 重層する時空―嘱目と永遠
3 画家の眼―叙景の構図と色彩
4 文人精神―風雅と隠逸への憧れ
5 想像力の源泉―歴史・芝居・怪異
6 日常と非日常
著者等紹介
揖斐高[イビタカシ]
1946年北九州市生。東京大学文学部卒業、東京大学大学院修了。博士(文学)。現在、成蹊大学名誉教授、日本学士院会員。著書に『江戸詩歌論』(汲古書院、読売文学賞)、『近世文学の境界―個我と表現の変容』(岩波書店、やまなし文学賞・角川源義賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テイネハイランド
14
図書館本。編者の揖斐高さんは、江戸期の漢詩の解説をさせるとこの人というくらい、私にとって信頼ができる研究者の方です。本書では、各種の(先行文献/解説書)を適切に引用しながら、蕪村の作品をわかりやすく紹介していて、このシリーズ(コレクション日本歌人選)の中でも優れた一冊といえるように思います。蕪村は、俳人のみならず職業画家(生活面では、画家が本業で俳諧は余技)でもあり、画家の眼をもって読んだ作品群があるとのこと。「 稲づまや浪もてゆへる秋津島」はその好例で、とてもスケールの大きな作品だと思いました。2021/03/17
木倉兵馬
2
読了してみて、与謝蕪村の詩を鑑賞するという行為は非常に知識が問われる、と感じました。まあ単純に美しい言葉だけから広がっていく景色や世界を味わうのも良いのでしょうけど、作者の意図を無視しないためにも古典や漢文などを読んでおくのがいいのでしょうね……。ちなみに私は解説がなければほとんど意図を取り損ねていました……。ただ、「草枯れて狐の飛脚通りけり」はこの前読んだ今昔物語集の芋粥の原話が元になっているのかなー、と思ったところその通りでもあったので好きです。2022/12/19
bookmari55
1
正岡子規の本を読んで、子規か蕪村の句を評価してると知り読んでみる。句を「写実的なもの」「絵画的なもの」「雅なもの」「想像力を活かしたもの」「日常非日常なもの」と分けて紹介。子規の評価はやはり「写実的なもの」に分類されたところに多かった。個人的には面白いなと思ったのは蕪村は画家でもあるので「絵画的なもの」に分類された句が好き。「ほとゝぎす平安城を筋違に」「春雨や小磯の小貝ぬるゝほど」中国の古典や古今和歌集、万葉集などの作品をヒントに作られた句も多く、昔の人の博学さにも驚かされた。2020/04/18