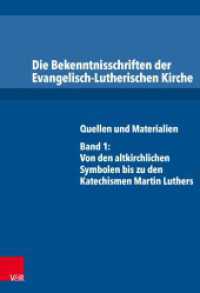出版社内容情報
江戸時代の孝は、誰もが善と信じて疑わない思想であった。
そのころの孝という道徳が持っていた活力と豊かさを掘り起こす。
「孝道徳」は、時に戦前の軍国教育と結びつけて考えられたり、また為政者による人民統制の手段と考えられたりと、とにかく堅苦しいイメージが強い。間もなく学校教育の場で「道徳」は、「特別の教科」として格上げされることが決定しているが、そこでは「また親孝行を教え込まれるのか」との危惧が伝わってくる。
果たして江戸時代からそれは、そのようなものであったのか。孝という道徳は、たしかに政治的な負の側面ばかりが目立つものであるが、本書は江戸時代の孝がもらたした文化的な側面や、人の動き、書物の動き、思想の動きに着目し、江戸時代に孝が持った肯定的な熱気と、そこから生じた多様な現象を明らかにすることで、江戸時代の孝に対する研究や一般的なイメージにおけるステレオタイプに異を唱える。
【本書を通して訴えたかったのは、江戸時代の孝に対する研究や一般的なイメージにおけるステレオタイプに異を唱えたい、ということである。「孝子良民の表彰は封建制度の強化策」という考えは、戦後になってから固定化されたものである。しかし江戸の孝を論じるとき、このような画一的な結論だけで良いのだろうか。少なくとも江戸時代の人は、孝をそのように批判的に見ていなかった。孝の多様で豊かなありようを享受していたはずである。このように考えて、実例をもとに新たな見方をさまざまに提示してみたのが本書である。読者が江戸の孝のポシティブな力を少しでも感じ取って下さったなら、本書は成功である。】…あとがきより
はじめに
一 なぜ江戸の孝なのか
二 近世孝文化の研究史
三 本書の研究姿勢
四 本書の構成
第一章 孝文化研究序説
第一節 孝子表彰への好意的なまなざし―十七世紀後半の全体像
一 江戸から見た孝とは
二 孝子表彰説話を受け入れる土壌
三 文字資料の伝播力
四 表彰されない逸話
五 情報圏と孝子説話
六 おわりに
第二節 西鶴は孝道奨励政策を批判しなかった―不孝説話としての『本朝二十不孝』
一 孝の奨励か批判か
二 実践と説話とのちがい
三 孝行説話の話型
四 不孝説話のからくり
五 序文は何を宣言したか
六 『本朝二十不孝』の不孝者
七 おわりに
第三節 表彰が人を動かし、作品を生む―駿河国五郎右衛門を例に
一 政治と文学のあいだで
二 対象作品と略年表
三 天野弥五右衛門長重との出会い
四 二度目の江戸行と饗応―作品一〔五郎右衛門像賛〕
五 五郎右衛門伝の依頼者―作品三「孝子今泉村五郎右衛門伝」
六 もうひとつの五郎右衛門伝―作品二〔五郎右衛門刷物〕
七 記念品としての作品成立―作品四〔六字名号父母画幅〕
八 おわりに
第四節 表彰は説話の起爆剤―駿河国五郎右衛門をめぐって
一 孝子伝は信用できるか
二 逸話のない孝子
三 五郎右衛門の説話資料
四 かわら版から儒者伝記へ―〔五郎右衛門刷物〕と「孝子今泉村五郎右衛門伝」
五 逸話の多様化―表彰から二年後以降の展開
六 表彰と説話との関係
七 おわりに
第二章 表彰と孝子伝の発生
第一節 綱吉による孝行奨励政策の背景
一 全国の大名と綱吉
二 寛永期まで(~一六四四)―芽生えの季節
三 正保~万治期(一六四四~一六六一)―はじまりは会津と岡山
四 寛文期(一六六一~一六七三)―松平忠房の参入
五 延宝期(一六七三~一六八一)―徳川光圀の参入
六 綱吉まで
第二節 偽キリシタン兄弟の流転―保科正之の孝子認定と会津藩における顕彰
一 忘れられた存在
二 対立する評価―?読耕斎「甲州孝子事記」?鵞峰「甲州里民伝」
三 全国と地方での発掘―?一雪『古今犬著聞集』?信斎「孝子伝」
四 会津藩の目覚め―?『会津孝子伝』
五 近世孝子伝と地元意識―?『会津孝子伝』
六 説話のゆくえ―?『日新館童子訓』ほか
七 おわりに
第三節 表彰と説話集とのあいだ―岡山藩
一 岡山藩に注目する理由
二 近世前期岡山藩の表彰と説話集
三 『続備陽善人記』の成立と文章
四 『備陽善人記』の作者と成立時期
五 記されない表彰―『備陽善人記』の文章(一)
六 記されすぎる表彰―『備陽善人記』の文章(二)
七 おわりに
第四節 宝物としての孝子伝―福知山藩・島原藩
一 孝子表彰と孝子伝執筆
二 忠房孝子伝の先駆性と特色
三 忠房の孝行奨励の全体像
四 忠房孝子伝の役割〈一〉―林家との関わりの中で
五 忠房孝子伝の役割〈二〉―孝子伝の流布
六 忠房孝子伝の役割〈三〉―表記と教訓
七 『本朝孝子伝』への影響
八 忠房孝子伝の変質
九 おわりに
第三章 孝子日本代表の形成
第一節 明代仏教がリードした江戸の孝子伝―元政『釈氏二十四孝』と高泉『釈門孝伝』
一 孝子伝と護法
二 孝子・元政
三 『釈氏二十四孝』
四 元政の「無為報恩」観
五 僧へ孝を説く
六 明僧・?宏の影響
七 明代仏教を踏まえた生き方
八 孝子説話の展開についての研究史
九 高泉『釈門孝伝』について
十 灯史の影響
十一 当代日本人僧の追加
十二 日本人僧追加の背景
十三 おわりに
第二節 儒者が選んだ日本史上の孝子
一 代表選出の季節
二 林羅山『十孝子』をもとめて
三 孝子の顔ぶれ
四 奏上文からの選出
五 仏教説話から孝子説話へ
六 林鵞峰の孝子選出―『本朝言行録』と『続本朝人鑑』
七 『本朝孝子伝』の古典章段
八 鵞峰・懶斎が選んだ孝子たち
九 依拠資料の違い
十 神と天皇の孝子―『本朝孝子伝』人選の特徴?
十一 仏教批判と典拠主義―『本朝孝子伝』人選の特徴?
十二 葬祭の重視―『本朝孝子伝』人選の特徴?
十三 人選の背景にあるもの
第三節 『本朝孝子伝』刊行直後
一 あまりに早い改編
二 修訂とその先後
三 七冊本と三冊本
四 なぜ改版されたのか
五 刊行後に寄せられた指摘
六 『仮名本朝孝子伝』へ
七 漢文版の著者自身による平仮名化
八 平仮名本出版の両面
九 神代に孝子をさがす
十 新たな文献の提示
十一 おわりに
第四節 弥作が孝子日本代表になるまで―水戸藩の表彰と顕彰
一 顕彰される理由は
二 弥作の表彰から、伝記が書かれるまで
三 弥作伝の系譜
四 百年の黙殺
五 文政期の碑建立と小宮山楓軒
六 弥作家再興と大場家
七 『野史』への入集
八 『幼学綱要』への入集
九 おわりに
第四章 藤井懶斎伝―いかにして『本朝孝子伝』は生まれたか
〈一〉墓碑銘
〈二〉武富廉斎『月下記』巻三「藤井懶斎」(抄)
元和三年(一六一七)丁巳 一歳~宝永六年(一七〇九)己丑 九十三歳
コラム
【家系資料】/【父・了現と懶斎の生地】/【実母と継母】/【兄弟姉妹】/【久留米藩時代の資料】/【久留米藩医としての活動】/【懶斎と旅】/【懶斎の友人と山崎闇斎】/【儒学の師に関する諸説】/【満田懶斎との混同】/【久留米藩士としての文事】/【久留米藩における和歌指導】/【寂源との交流】/【武富廉斎との交流】/【居所〈一〉永昌坊寓居期】/【京都での佳会】/【懶斎の著作目録】/【常盤木】/【居所〈二〉北野】/【懶斎著作と署名】/【一文字署名のはじまり?】/【書肆・西村孫右衛門】/【長男・革軒】/【次男・象水】/【居所〈三〉千本】/【居所〈四〉鳴滝隠棲】/【西寿寺の再興】/【三輪執斎】/【増田立軒】/【淡路の懶斎連】/【金蘭斎との混同】/【四書解説】/【戦国武将・真鍋祐重との関係】/【懶斎と僧との交流】/【藤井懶斎の果たした役割】
あとがき
英文要旨[Abstract]
索引
勝又 基[カツマタ モトイ]
1970年、静岡県御殿場市生まれ。金沢大学文学部卒業、九州大学大学院文学研究科(修士・博士)修了。博士(文学、九州大学)。日本学術振興会特別研究員PD(東京大学)などを経て、2005年より明星大学日本文化学部専任講師。2014年4月よりハーバード大学ライシャワー日本研究所客員研究員(2015年3月まで)。2015年より明星大学人文学部教授。著書『落語・講談に見る「親孝行」』(2011年、NHK出版)、『孝子を訪ねる旅』(2015年、三弥井書店)、編著『『本朝孝子伝』本文集成』(2010年、明星大学)ほか。
内容説明
「孝子良民の表彰は封建制度の強化策」という考えは、戦後になってから固定化されたものである。少なくとも江戸時代の人は、孝をそのように批判的に見ていなかった。江戸の「孝」は、誰もが善と信じて疑わない思想であった。実例をもとに新たな見方をさまざまに提示。今とは違う、その活力と豊かさを掘り起こす!
目次
第1章 孝文化研究序説(孝子表彰への好意的なまなざし―十七世紀後半の全体像;西鶴は孝道奨励政策を批判しなかった―不孝説話としての『本朝二十不孝』;表彰が人を動かし、作品を生む―駿河国五郎右衛門を例に;表象は説話の起爆剤―駿河国五郎右衛門をめぐって)
第2章 表彰と孝子伝の発生(綱吉による孝行奨励政策の背景;偽キリシタン兄弟の流転―保科正之の孝子認定と会津藩における顕彰;表彰と説話集とのあいだ―岡山藩;宝物としての孝子伝―福知山藩・島原藩)
第3章 孝子日本代表の形成(明代仏教がリードした江戸の孝子伝―元政『釈氏二十四孝』と高泉『釈門孝伝』;儒者が選んだ日本史上の孝子;『本朝孝子伝』刊行直後;弥作が孝子日本代表になるまで―水戸藩の表彰と顕彰)
第4章 藤井懶斎伝―いかにして『本朝孝子伝』は生まれたか
著者等紹介
勝又基[カツマタモトイ]
1970年、静岡県御殿場市生まれ。金沢大学文学部卒業、九州大学大学院文学研究科(修士・博士)修了。博士(文学、九州大学)。日本学術振興会特別研究員PD(東京大学)などを経て、2005年より明星大学日本文化学部専任講師。2014年4月よりハーバード大学ライシャワー日本研究所客員研究員(2015年3月まで)。2015年より明星大学人文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 野ばらの森の乙女たち 分冊版(3)