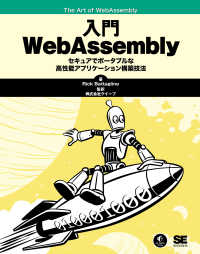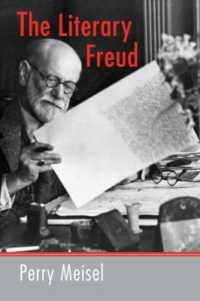内容説明
小説のみならず、演劇、映画、ラジオドラマ、テレビドラマまで自ら手掛けた、メディア・アートの先駆者、安部公房。その多彩な表現活動を分析しつつ、生涯を俯瞰する、安部公房入門書。
目次
第1部 安部公房とはなにものか(“リテラリー・アダプテーション”という思想;マルチメディア演劇への道)
第2部 作品論への誘い(『壁あつき部屋』論―罪責のゆくえを追う;戯曲『どれい狩り』論―「主役」としての肖像画;『砂の女』論―「死と性病」の再考から)
著者等紹介
木村陽子[キムラヨウコ]
1972年、東京生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。専攻は日本語・日本文化。2008年から2012年まで早稲田大学演劇博物館のグローバルCOE研究生、研究員、非常勤職員として演劇映像学を研究。2009年から現在まで桜美林大学北東アジア総合研究所の客員研究員として日中関係学を研究。東京学芸大学非常勤講師、同済大学(中国)特別招聘副教授(専任)を経て、埼玉東萌短期大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
山田太郎
29
大学生の時読んだ記憶があるけど、よくわかんなかったような気がする。ちょっと読んでみようかという気がおきてきたので、いい本なんだろうこの本。作者名前が地味だな。2013/07/17
ハチアカデミー
9
マルチメディア作家として安部公房を捉えた一冊。小説以外にも、テレビドラマ・演劇・映画など、様々な方法で作品を発表した公房を、リテラシー・アダプテーション、つまり複数の創作方法によって、作品を作り変えていった作家として論じている。同時代の安部公房受容者は、おそらく同時代の者が見ていたであろう安部公房を知らない。特に舞台というその瞬間にしか体験できないものを論じる難しさがあるし、ゴシップ的な話も知らない。それらを含めた安部公房論を書けるのは、同時代者や知人・友人の存命ないましかない。砂の女読解はやや強引。2013/06/08
mstr_kk
5
安部公房「入門書」。前半の、複数メディアとの関わりで安部を捉える、という部分は、かなり演劇に偏ってはいるものの、たいへんありがたい。『砂の女』論はかなり大胆な読みが面白いが、淋病の隠喩を特権化しすぎ。さまざまなモチーフや手法の組み合わせを読んでいないので、小説論としては「変種」や「珍種」にとどまるといわざるをえない。「入門書」に収録して良かったのか、疑問である。2013/05/23
ホッタタカシ
4
「小説家」だけでなく、劇作家、放送作家、演出家、映画監督でもあった安部公房の魅力を再評価すべしという本がついに出たことは喜ばしい。前半の評伝パートは、受賞歴や細かい人間関係に妙にこだわるなど視点が下世話な方向に流れがちだが、安部ファンには新鮮な情報も多く楽しい。後半は作品論だが、『壁あつき部屋』、『どれい狩り(初演版)』のモチーフ解説、性病文学として読み解く『砂の女』など斬新な論を揃えつつ、作品読んだ人(マニア)向けなのは惜しい。「多メディア作家・公房」の魅力を広く啓蒙する内容でもよかったのでは。2013/05/30
chaki
3
高校生の時に安部公房の小説をいくつか読んでいたので、読み直そうと思っていたタイミングでこの本を読んでみた。正直、劇作家とか沢山のメディアで積極的に活動してたんだね。小説家以外の公房さん知らなかった。この本も小説の事はそれ程出てこなくて演劇などの活動が中心に書かれていて、私の期待したものではなかった。小説読みます。2014/01/19
-
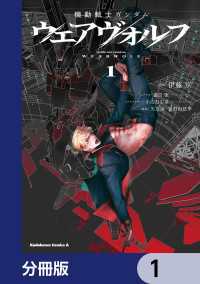
- 電子書籍
- 機動戦士ガンダム ウェアヴォルフ【分冊…
-

- 電子書籍
- 没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法…