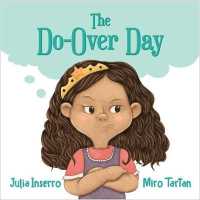内容説明
西行や芭蕉も、その足跡を追いかけた旅の歌人。歌に魅了された「数寄」の先達。
目次
馬(別るれど安積の沼の(安積沼の駒)
かくしつゝ暮れぬる秋と(馬との別れ))
交友(今更に思ひぞ出づる(藤原保昌)
いづくとも定めぬものは(藤原兼房) ほか)
旅と山里(昔こそ何ともなしに(伏見里)
神無月寝覚めに聞けば(落葉の音) ほか)
奥州の旅(東路はいづかたとかは(東路)
都をば霞とともに(白河関) ほか)
歌合ほか(時鳥き鳴かぬ宵の(時鳥の声)
世の中を思ひ捨ててし(思ひ捨てし身) ほか)
著者等紹介
高重久美[タカシゲクミ]
1943年愛媛県生。お茶の水女子大学卒業・大阪市立大学大学院修了、博士(文学)。現在、大阪市立大学文学研究科都市文化研究センター研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
303
能因の百人一首歌は「嵐吹く御室の山の紅葉ばは…」だが、私にはこれが代表歌とは思えない。むしろ最も人口に膾炙した「都をば霞とともに立ちしかど秋風ぞ吹く白河の関」の方が歌としても優れているように思われる。これが西行の「都出でて逢坂越えし折までは心かすめし白川の関」を生み、源頼政の等類歌「都にはまだ青葉にてみしかども紅葉散りしく白河の関」を生み出したのであるから。芭蕉は、これらの古歌に圧倒されたか、ここでは『おくの細道』に句を採択せず、曾良句の「卯の花をかざしに関の晴着かな」でお茶を濁している。2022/10/06
はちめ
1
長く出版を待っていたのでまずその点で感慨深い。初めて能因の歌をまとめて読んで、そのことには満足。ちょっと以外だったのは、先入観として能因という人は世俗から完全に離れて生きた人だと思っていたけど、案外世俗との繋がりをしっかり保ちながら生きた人だということ。多くの旅をしていることも含め、西行の生き方と酷似しており、出家の決断の時から大きな影響を与えているのは間違いない。西行の出家の決断に能因の出家が決定的な影響を与えたという説はあったかな?2012/12/01