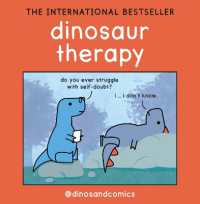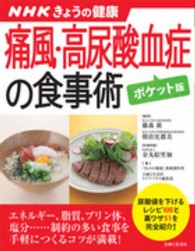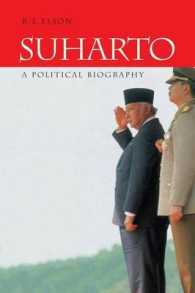出版社内容情報
かつて日本では『経済白書』という経済分析の書が、経済企画庁から毎年刊行されていた。『経済白書』は政府の景気感を示し、経済政策の基盤となるものだけに、各省庁との意見調整は日常茶飯事であり、取り上げるテーマについても慎重な取り扱いが必要とされた。経済白書のみならず経済分析には知られざるドラマがあったのだ。
本書は、ニクソンショック、石油危機から経済摩擦、バブル経済、デフレまで日本経済の課題に官庁エコノミストして対峙してきた小峰氏が戦後経済の軌跡を読み解く日本経済研究センターのサイトでの連載「小峰隆夫の私が見てきた日本経済史」を書籍化するもの。
小峰氏は1969年に大学を卒業して経済企画庁(現内閣府)に入ってから今日に至るまで、幾度も経済白書執筆に携わり、40年以上もの間日本経済を観察し続けてきた。本書は、経済白書が出来るまでの攻防、経済論争の舞台裏など筆者の経験を踏まえて、日本経済の歩みをたどり直す生きた現代経済史である。既刊の『平成の経済』は通史として高く評価され、読売・吉野作造賞を受賞。本書はより私的な体験を踏まえた内容となり、小宮隆太郎、根岸隆、金森久雄、香西泰など名だたる研究者・エコノミストとのエピソードも交えて記述する。
小峰氏が本音ベースで執筆している本書は、日本経済を考えるうえで有用な視点を数多く提供する経済史となる。
内容説明
枕詞は疑うべし―。ニクソン・ショック、石油危機から経済摩擦、バブル崩壊、デフレまで40年以上にわたって日本経済の課題に対峙してきたエコノミストは、タブーを恐れずにいかに問題の本質を突き詰めていったのか。経済白書完成までの攻防、経済計画作成の舞台裏、経済分析をめぐる論争などの知られざるドラマを、小宮隆太郎、根岸隆、金森久雄、香西泰など名だたる研究者・エコノミストのエピソードも交えて明らかにするユニークな日本経済論。
目次
第1章 タブー死すべし―ニクソン・ショックと悲劇の経済白書
第2章 石油危機の時代
第3章 経済摩擦と経常収支不均衡について考える
第4章 月例経済報告を振り返る
第5章 経済白書とは何か
第6章 エコノミスト修業時代
第7章 経済白書ができるまで(前編)―内国調査課長就任から原案執筆まで
第8章 経済白書ができるまで(後編)―各省調整から発表まで
第9章 経済白書で分析してきたこと
第10章 官の世界で経験し考えてきたこと
著者等紹介
小峰隆夫[コミネタカオ]
1947年3月生まれ。2023年4月大正大学地域創生学部客員教授。ほかに、現在、日本経済研究センター理事・研究顧問、中曽根康弘世界平和研究所研究顧問などを務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
しゅー
takao
Kooya
すのす
-
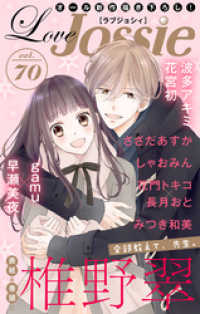
- 電子書籍
- Love Jossie Vol.70 …