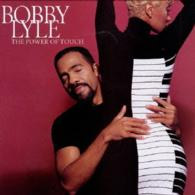- ホーム
- > 和書
- > コンピュータ
- > プログラミング
- > SE自己啓発・読み物
出版社内容情報
『コンピュータはなぜ動くのか』19年ぶり、待望の改訂第2版!
「これからの10年も通用する基本」を身につけよう!
ハードウエア、ソフトウエア、データベース、ネットワーク、セキュリティというコンピュータを使いこなすうえで必要な知識をこの1冊で解説します。
ハードウエアの基本的な仕組み(プロセサ、メモリー、入出力)から、ソフトウエアの実際(プログラム、アルゴリズム、データ構造、データベース、ネットワーク)とシステム構築までをカバー。これからプログラマやSEを目指す入門者から、基本をひと通り学びたい文系エンジニア、さらには、もう一度学び直したいベテランエンジニアまで、コンピュータを動かして成果を得ることの楽しさと仕組みを知りたい人に役立つ内容です。
【改訂のポイント】
今後10年通用するよう内容を全面的に更新。具体的には以下の通りです。
・「コンピュータを作ってみよう」では「COMETⅡ/CASLⅡ」に対応。
・プログラム部分はPythonでの記述に一部変更。
・データベースではMySQLに変更。
・暗号化では共通鍵暗号方式から公開鍵暗号方式に変更。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっしー@challenge
5
■アセンブラがCPUとメモリを仲介するイメージをCASL Ⅱで理解。 ■プログラムフローの基本は①順次②分岐③繰り返しの3つ。メモリー視点ではジャンプ命令で行き来。 ■アルゴリズムには定番がありユークリッド互除法は機械的。番兵を用いるとアルゴリズムがスリム化される。 ■データ構造は変数で配列を用いるとメモリを効率的に確保できる。 ■オブジェクト指向は上位のクラスでメンバー(変数と関数)の固まりを作る概念。 ■公開鍵暗号方式は1-10の数値をべき乗と除算の余りで一致する部分を採る。 ■XMLは自身の課題。2023/02/02
yu
3
CPU、I/Oをはじめとしたハードウェアの部分から、データベースやプログラミング、ネットワーク、暗号化の仕組み等、コンピュータが動く仕組みと取り巻く技術の基礎的な概要をわかりやすく解説している。 本書で各構成要素の概要を掴んでから、各要素の詳細を学ぶと理解がスムーズに思える。2024/07/12
Ganymede
3
▼P59:「1と2を加算する」という課題を使って、コンピューター内部では何をしているのか?を学ぶ。人間が書いたプログラムが二進数に変換され、メモリーやCPUで次々と処理されていく様子を確認できる。▼P86:プログラムの流れを考えるフローチャートの描き方を「じゃんけんゲーム」で学習する。現実世界で行われている手作業を、情報処理に置き換える手順を学ぶ。▼P108:「エラトステネスのふるい」を例に、解法となるアルゴリズムは複数あることを学ぶ。どれでも素数判定はできるが計算回数の違いが処理スピードの差に出てくる。2023/06/01
SABA
2
itパスポートで勉強している箇所がいくつかありました。プログラマーでも出世するにはコミュニケーション能力が重要といわれている所以が理解できました。2026/02/22
浦井
2
1〜3、12章だけ読んで後は流し読み。2025/07/12