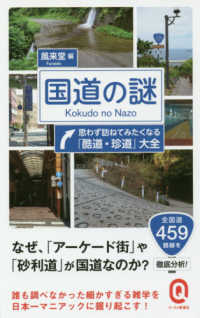内容説明
落書きのような「作品」がなぜ何億円もするのか?元経済紙記者の美大教授がお金とアートの切っても切り離せない関係を明かす。
目次
第1章 1枚の絵画から見えてくる経済の成り立ち
第2章 浮世界に見る商業アート
第3章 時代とともに変わる美術の価値観
第4章 パトロンとしての美術館
第5章 贋作と鑑定
第6章 美術作品の流動性を支える仕組み
第7章 これからの美術の経済
著者等紹介
小川敦生[オガワアツオ]
多摩美術大学芸術学科教授、美術ジャーナリスト。1959年北九州市生まれ。東京大学文学部美術史学科卒業。日経BP社の音楽・美術分野の記者、『日経アート』誌編集長、日本経済新聞社文化部美術担当記者等を経て、2012年から現職。「芸術と経済」「音楽と美術」などの授業を担当。日本経済新聞本紙、朝日新聞社「論座」、ウェブマガジン「ONTOMO」など多数の媒体に寄稿。多摩美術大学で発行しているアート誌「Whooops!」の編集長を務めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
74
神聖な芸術に「お金の話」はハシタナイと思いながら、覗いてみたくなるのがゲスの卑しさ。でも、日経新聞の美術担当記者を経て多摩美大教授である著者は、ビジネス・芸術の双方に精通され、何より美術や画家に対する深い愛情と尊敬が滲み出ていて、内容は卑俗ではない。美術の経済が、コレクター、画商、オークション、美術館などによって支えられていることが分かる。日本の国立美術館4館合計の年間作品購入費がたった40億円、絵画の真贋鑑定費用は5万円。日本のオークション市場規模が200億円(中国は兆円)など、いろんな数字にも出会う。2020/12/18
yyrn
31
『最後のダヴィンチの真実』(近年発見され修復後に510億円で落札された絵サルバトール・ムンディに関する本)を読み、美術をお金に絡ませて論じるのは冒涜だと感じたが、本書でいうとおり、お金が回らなければ新たな美術も生み出せないというのも道理で、「美術」を生み出すためのお金にまつわる話はうなづくところが多かった。昔にあってはパトロンやお抱え絵師の話、中産階級が出現した近世にあっては画商やコレクターの話、近現代にあってはオークションや美術館の果たす役割の功罪などの話のほか、贋作と鑑定の話や、一点ものの「美術品」⇒2021/01/18
イリエ
20
何だかイケナイ、アートとお金の話。本著ではその理由も含め、人生を豊かにする大切な気づきがありました。序盤と終盤は刺激的で面白いです。途中は、物知りオジサンの話に付き合っている感じはありますが、読みやすいです。2025/06/28
エムパンダ
10
明治に一部の画家が積極的に書籍の装丁や挿絵の世界に参入した背景に、日本にはもともとデザインとアートの区別がなかったためという話があり、美術とお金にまつわること以外でも美術史に根差したエピソードが含まれていて興味深く読んだ。パトロンとしての美術館、贋作、芸術祭の章も、素人でもわかりやすい。2021/03/24
M
8
文化として美術が生活の歴史と歩みを重ねているという側面を美術の提供者側から語られるようになったという点に時代性の変化のようなものを感じている。物に溢れた現代消費社会で、値段がつけられない、あるいは法外な値がつけられる美術をどう捉えるのかというのは様々な視点がありうるが、コロナという厄災を経過して、美術の持つ価値及び、意味も問い直されつつあるのだろう。娯楽と美術は単純な優劣などではなく、歴史的価値は来歴の喪失と相反し、同時に新規さの基準にもなりえ、他国及び他文化との比較による共通の話題にもなりうるからだ。