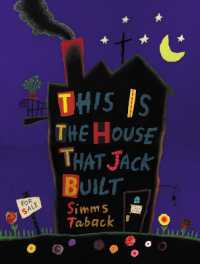出版社内容情報
作曲家の伝記は、まずこの本からスタート。生涯・作品・資料の三つの項目で統一したシリーズ。このワーグナーでは、作曲ばかりでなく多面的な活動も描き、現在まで続くワーグナー家のことも扱っているのがユニーク。
内容説明
作曲家、指揮者、おたずね者、著述家、経営家、教祖…ドイツ・オペラの大成者の多面的肖像を描ききり、現在までの「バイロイト王朝」の系譜をも跡づける。巨人ワーグナーの全貌がいま明らかになる。
目次
生涯篇(演劇少年―ライプツィヒとドレスデン(一八一三‐一八三三)
新米指揮者―ヴュルツブルク、マクデブルク、リガ(一八三三‐一八三九)
野心家―パリ(一八三九‐一八四二)
宮廷楽長―ドレスデン(一八四二‐一八四九) ほか)
作品篇(『さまよえるオランダ人』三幕のロマン的歌劇;『タンホイザーとヴァルトブルクの歌合戦』三幕のロマン的歌劇;『ローエングリン』三幕のロマン的歌劇;『トリスタンとイゾルデ』三幕の劇(ハンドルング) ほか)
資料篇
著者等紹介
吉田真[ヨシダマコト]
1961年、東京生まれ。慶応義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得。専攻はドイツ文学(ワーグナー研究)。慶応義塾大学講師。同大学などで、ドイツ語、ドイツ文学、オペラの講義を担当するかたわら、『音楽の友』『レコード芸術』などに評論を執筆
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
碧緑(あおみどり)
13
来月、ついにあこがれのバイロイト音楽祭に行くことになり、その予習として。ワーグナーは音楽の英才教育は受けておらず、楽器の腕前も作曲に必要なピアノを少々、という程度。音楽教育は大学や専門学校ではなく、教会に所属していた人に個人授業を受けていた。それなのに自分の才能を信じて疑わなかったし、若い頃から自論を持ち論文を大量に書いたという。現代の「指揮者」像の基礎を作ったのもワーグナーだった。反ユダヤ的な姿勢は、彼を批判するメンデルスゾーンなどユダヤ人音楽家への反発心からだとしても、論文にとして残ったのはまずい。2025/06/12
tieckP(ティークP)
6
ワーグナー(及びバイロイト音楽祭を管理する子孫)の伝記と主要楽曲の構成・あらすじ・解説。毀誉褒貶相半ばする(というか「人間的には褒められないが芸術的にはすごい」と評価されがちな)人物の伝記としてはかなり爽やか。浪費癖や人種差別についても述べつつ、人間関係での対立の多くは誤解によるものとして根拠を説明し、同時代に多くの人々を魅了したワーグナーとして描けている。彼の先駆者としての意義を、無調性音楽やキャラクターグッズやオーケストラピット等について述べつつ、専門知識に寄り過ぎないので興味本位の素人でも読めた。2021/07/06
Yoshi
2
ドイツ・オペラの巨人リヒャルト・ワーグナーの人生と作品。 さまよえるオランダ人、ニュルンベルクのマイスタージンガー、ラインの黄金、ヴァルキューレは見ているのだがめちゃくちゃ壮大かつ長いが、ぐいぐい引き込まれる魅力ある作品だった。 浪費癖や尊大な人格と書いてあり、そういう人間だからこそこれだけ大きなものが作れたのだろうとか。 パリで失敗後にパイロイトで劇場をそのままつかって祝祭する案もオペラ作者だからこそのアイデアなのだろう。 今もワーグナー家が存続しており、一度パイロイトへ行ってみたいと思った。2020/09/29
佐月
1
ワーグナーという作曲家の生涯と、彼の作品概要がまとまった贅沢な1冊。分かりやすい文章で書かれているので音楽に明るくない私でも大変楽しんで読むことができました。また、この本を読むことでオペラに興味を持つことができました。ワーグナーについてはwikiを読んでいると破天荒な作曲家だという印象を受けましたが、伝記という形で彼の生涯を見つめることができたので見方が変わり、偉大な作曲家への尊敬の念が深まりました。2020/06/27
kotohoge
0
ざっと読む分にはよかった2017/10/08