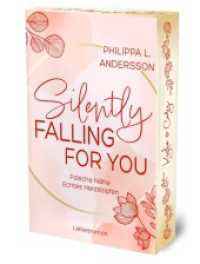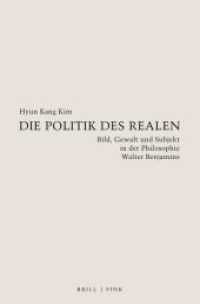内容説明
調性が崩壊せず、“無調”も実在しないとしたら…20世紀以降の音楽にほんとうは何が起こったのか?音の縦の関係性を軸に、音楽史の再検討を迫る画期的論考。
目次
プロローグ―ドミナントなき時代
第1章 「無調」とは何だったのか
第2章 シェーンベルクを読み直す
第3章 無調と調性の間
第4章 無調と調性の修辞学
第5章 クルシェネクの「転向」(無調の政治学1)
第6章 もうひとつのダルムシュタット(無調の政治学2)
インテルメッツォ―ニコラス・ナボコフと「無調」
第7章 隠れた水脈―八音音階という魔術
第8章 調性の回路
第9章 音律と倍音がつくる世界
第10章 時間の軌道
エピローグ―中心のない現代
著者等紹介
柿沼敏江[カキヌマトシエ]
静岡県出身。カリフォルニア大学サンディエゴ校博士課程修了。ハリー・パーチの研究で博士号取得。主要訳書:アレックス・ロス『20世紀を語る音楽』(みすず書房、2010年、ミュージック・ペンクラブ音楽賞)ほか。2019年3月まで京都市立芸術大学音楽学部教授。現在、京都市立芸術大学名誉教授。江戸時代に広まり、現代に伝承されている「一絃琴」の名取でもある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
70
12の半音を平等に全部使えば「無調」になる? 最初の7つが「ドレミファソラシ」でもいいのか? と、昔から変だな、と思ってましたが。シェーンベルクの12音技法をメインに、「無調」が生んだ波紋や騒動、20世紀音楽への影響と余波を述べた、大変おもしろい本。確かに、全音音階は鉄腕アトム。8音音階のメシアンを聞くと、素人耳には武満徹みたいに聞こえ、シェーンベルクの弦楽四重奏も、何かの調で一貫しているかのよう。無調ではなく汎調性というのもうなづける論。ぜひ聞きたい20世紀末以後の曲も多く紹介されている。調性は幅広い!2020/02/29
ひばりん
12
シェーンベルクファンとしては、ようやくこういった本が出たか~という感想。ただシェーンベルク周辺(シェーンベルクのやったことが〈無調〉と要約されていく過程)はよく整理されているものの、シェーンベルクじたいについて何らか新しいことが言われている本ではない。現代音楽論をゆるく書く方向に本の構成が流れてしまった。もっと渦を巻くようにシェーンベルクという不思議の原点を深堀りしてほしかったところ。惜しい論点がいくつもある。2021/08/25
おだまん
4
現代音楽(20世紀音楽)のよき指南書。そばに置いて色々聴きたいなぁ!2020/08/30
Nepenthes
3
調性も無調も感性なんだなという感想。乱調の美、無調の美。 2025/03/26
毒モナカジャンボ
2
面白いが、現代音楽とはなんだったのか、という気持ちになり、それはもう現代音楽が(顧みるものの少ない)歴史になったということだろうなという気持ちにもなる。2024/05/05
-

- 電子書籍
- めじとやも 2 カドコミ