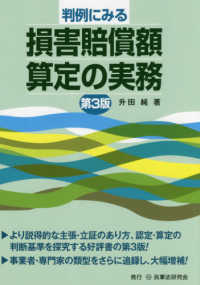出版社内容情報
受賞作『魂のエヴァンゲリスト』『マタイ受難曲』をはじめ、多くの充実の書で読者の篤い信頼を獲得している氏による「バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、ワーグナー論集」。
著者:磯山雅(イソヤマ・タダシ)
1946年東京生まれ、東京大学文学部卒業、同大学院美学・芸術学博士課程修了。現在国立音楽大学教授、専攻は音楽美学・西洋音楽史・バッハ研究。多彩な活動を展開中。
内容説明
音楽が伝えるものとは?音楽が聴く者の内面にもたらすものとは?『魂のエヴァンゲリスト』(辻荘一賞)、『マタイ受難曲』(京都音楽賞)を著した気鋭の音楽学者による、渾身のバッハ、ワーグナー…論の登場です。音楽への感動・情熱を根底におき、「キリスト教と音楽」を中心テーマに研究を深めてきた著者が長年にわたって綴った濃密な作曲家論であり、同時にオルガンについてのやさしく詳細明快な解説や、一三種の「パルジファル」録音の聴き比べなども収録した、バラエティに富んだ充実の書である。クラシック・ファンの基本ライブラリーとなる一冊。
目次
第1章 J.S.バッハの音楽(結婚カンタータ「満たされたプライセの町よ」BWV二一六が甦るまで;J・S・バッハの作品概念;オルガニスト、バッハ;創造性と教育―バッハのクラヴィーア音楽;バッハの視覚・視覚のバッハ;生きなさい、死になさい、ここに憩いなさい―バッハにおける「目覚め」の考察;マニフィカト、ルター、バッハ―「マリアのほめ歌」の解釈をめぐって)
第2章 古典派の音楽(モーツァルトの「クレド」書法;モーツァルトとバロック・ポリフォニー;ベートーヴェンにおけるダイナミックなソナタ形式の発明ベートーヴェンからの抜粋―“第九”の通念を問い直す)
第3章 ワーグナーとロマン派の音楽(ワーグナーにおける救済概念の深化;陰画としての「神々のたそがれ」―ワーグナー解釈の一つの試み;「パルジファル」における聖の二重構造;愛‐信仰‐希望?―ライトモチーフにたどる「救済」の音楽表現;“パルジファル”演奏史―一三のCDを比較する;すべての聴衆に開かれた福音―“ドイツ・レクイエム”の成立まで;グスタフ・マーラーの現代性―悲劇的世界をひたす愛の力)
著者等紹介
礒山雅[イソヤマタダシ]
1946年、東京に生まれる。松本深志高校から東京大学に進み、同大文学部と大学院で、美学芸術学を専攻。1977年、国立音楽大学の専任教員となり、現在同大学教授。専攻は音楽美学・西洋音楽史で、とくにバッハ研究で知られる。1985年、『バッハ/魂のエヴァンゲリスト』(東京書籍)により、第1回辻荘一賞を授与される。2007年より日本音楽学会会長。毎日新聞の音楽批評執筆者、大阪いずみホール音楽ディレクターとして、実践にもかかわっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どら猫さとっち
しお
-
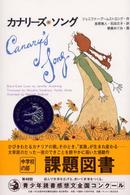
- 和書
- カナリーズ・ソング