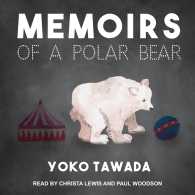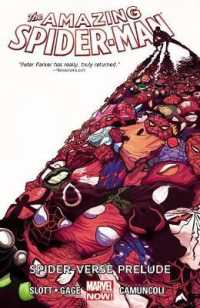出版社内容情報
2025年3月に東京藝術大学を退任する塚原康子教授と、東京藝術大学大学院音楽研究科の日本音楽史研究室において学び、藝大やその他の大学院で博士号を取得した卒業生を中心とする23名による研究論文集。
塚原教授のおもな研究テーマは、 現在の日本の音楽界の直接の出発点となった明治期の伝統音楽の変容と西洋音楽の受容についてである。過渡期の日本の音楽を多角的に見つめた研究手法はまさにフロンティアであり、その薫陶を受けたゼミ生も、近世(江戸時代)古代・中世・近世から近現代、日本からアジア、都市から周縁へと、異なる時代や地域にまたがる幅広い研究テーマと取り組んでいる。
本書では、その成果の一端が「つながる/つながり」をキーワードに5つの章にわけて示されている。
目次
第一章 近現代日本の音楽文化とつながる(昭憲皇太后と音楽;音楽取調掛・東京音楽学校における外国人教師たちの活動―近代日本における音楽教育史の再考に向けて ほか)
第二章 江戸時代の音楽文化とつながる(蟹養斎の俗楽論―『日本楽説』『猿瞽問答』をもとに;近世中後期の歌舞伎にみる在郷唄点描 ほか)
第三章 音楽構造・楽器文化とのつながり(琵琶譜に見る“三十二相”の音曲構造―『声明譜妙音院御作』をめぐって;室町後期から江戸初期の能管の「音取」―旋律の特徴を中心に ほか)
第四章 音楽文化にみる都市と周縁のつながり(江戸期吉原遊廓における音楽文化の研究―江戸文学の記述をめぐって;明治期の京都における演奏会―京都音楽会に着目して ほか)
第五章 東アジアの音楽文化とつながる(算賀と朝覲行幸における奏楽―平安前期の記録類から;戦時下北京における日本人音楽家の軌跡―北京における西洋音楽受容の一側面 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme
-
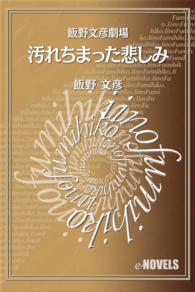
- 電子書籍
- 飯野文彦劇場 汚れちまった悲しみ
-
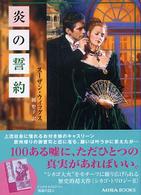
- 和書
- 炎の誓約 Mira文庫