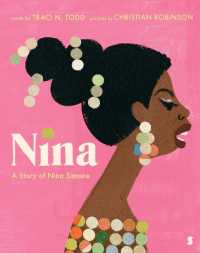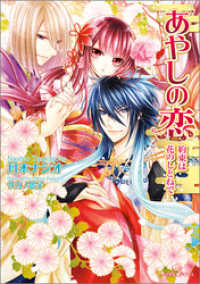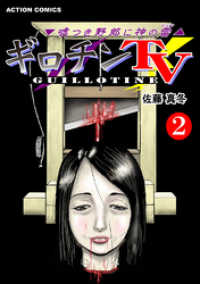出版社内容情報
「千と千尋の神隠し」に描かれた風景など、人々が「妖怪が出そう」と感じる風景に共通する謎を読み解く、ユニークな日本文化論。
内容説明
本書では、日本に古くからある、怪異・妖怪文化に焦点を当て、民俗地理学的な方法を中心に、民間伝承だけでなく、映画や小説、絵画などにも描かれた、怪異・妖怪の背後にある風景を、広く眺め渡した。
目次
怪異の見える風景
怪異の体験とことば
妖怪の走る風景
伝承集団の見た妖怪
頭のなかの妖怪地図
妖怪の二つの場所
『千と千尋の神隠し』に描かれた怪異世界の風景
怪異世界と心のなかの景観
現代日本人の怪異世界イメージ
廃墟と幽霊・怪異世界
現代の廃墟と近代化遺産
妖怪の出没する場所と年代
著者等紹介
佐々木高弘[ササキタカヒロ]
京都学園大学人間文化学部歴史民俗学専攻教授・国際日本文化研究センター共同研究員。1959年兵庫県生まれ。大阪大学大学院博士課程中退。歴史・文化地理学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
68
後半「千と千尋の神隠し」にからめて、怪異の風景が何を元に発生するかを追求する。資本により画一化された街並みを見慣れた現代人には、昭和初期の建築も怪異の風景にふさわしいものと化す。それが現代という時代だということか。著者の専門は地理学とのことで、フォークロアのフィールドワークで、同じテーマであっても、語られる内容が集落ごとの立場を反映して変化することを発見。怪異も現実の社会情勢に左右される存在だったとは。2019/08/22
Arisaku_0225
13
この本は妖怪(怪異)が「見える風景」とはどのようなところかを論じる。曰く、怪異が見える風景とは外の世界(外的世界)と頭の中の世界(内的世界)が交わった時である。例えば、何かしらの精神的ストレスを抱えた人間が怪異を見やすいのはそのせいである。また、「廃墟」も現実世界と過去の世界の中間地点であると説き、人々はそこに「何か」を見出し、それが日本では「妖怪」として語り継がれた。「妖怪」「幽霊」ではなく、それが何故そこで見られ、語り継がれてきた本質的な理由を探ろうとした挑戦的な研究と言えるのかもしれない。2022/08/08
夏目
11
化物語で怪異という単語を知って以来,なんだか怪異という単語に反応するようになり,読んでみた. 怪異と人は密接に関係しているように感じた!!2011/06/16
なー
7
怪異を説明のつかない不思議とするのではなく、地域・民族・言い伝え等の地理学的な観点から読み解いた本。前半は徳島の首なし馬伝説、後半は映画千と千尋の神隠しに見られる怪異の風景をメインに書かれています。ちょっと理屈っぽくて強引な展開だったけど、こういうの大好きです。ある怪談話を地域の特性や歴史を知った上で目線を変えたらどんな話になるのか等、物語が二倍三倍に膨らむ気がします。とても楽しく読めました。2019/08/10
佐倉
5
四国に現れる頭のない馬の怪異、クビキリウマについて人文地理学の観点から考察するのがメインテーマ。一見よくある妖怪に感じられるクビキリウマだが、その伝承を考察すると背景には「吉野川の氾濫で藍作が主流となった」という歴史的事実�や「藍商人と藍作人の経済的断絶」があったことが明らかになっていく。時代や人、文化の断絶により怪異が生まれるという話は非常に興味深い。2022/08/29