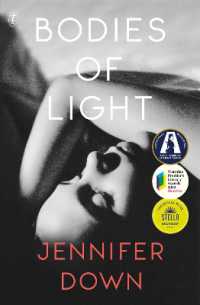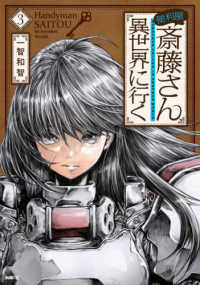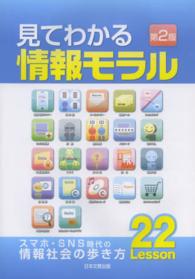出版社内容情報
【セールスポイント】
Linuxのカスタマイズに関する情報をコンパクトにまとめて紹介。
【発刊の目的と内容】
Linuxのカーネルや各サービスをより早く動かすためのチューニング法を紹介。カスタマイズに必要な知識やチューニングの概要から、パフォーマンスチェック、ボトルネックの把握法、個別サービスでのチューニング方法、Webサーバのパフォーマンス向上まで、チューニングの全般にわたって解説している。カーネル2.4系にも対応。
【購読対象者】
Linuxシステムの開発者
企業内でLinuxシステムの管理者
Linux中級者
システムアドミニストレータ的立場の人
【詳細目次】
第1章 パフォーマンスチューニングの概要
1.1 パフォーマンスチューニングとは何か
1.2 なぜチューニングが必要か?
1.3 何が調整できるのか?
1.4 パフォーマンスチューニングの目的を 明確にする
1.5 クリティカルリソースの識別
1.6 クリティカルリソースの要件を最小限にする
1.7 リソースの割り当てに優先順位をつける
1.8 方法論
1.9 パフォーマンスアナリストの役割
1.10 ユーザとパフォーマンスの関係
1.11 まとめ
第2章 パフォーマンスチューニングの側面
2.1 オペレーティングシステムの構造
2.2 カーネルアーキテクチャ
2.3 仮想メモリの概要
2.4 ファイルシステムのキャッシング
2.5 I/Oの概要
2.6 NFSパフォーマンス
2.7 方法論
2.8 測定
2.9 解釈と分析
2.10 チューニングかアップグレードか?
2.11 リスク評価とチューニング
2.12 結論
第3章 Linux用の一般的なUnixパフォーマンスモニタリングツール
3.1 この章で取り上げるツールの範囲
3.2 結果の解釈とその他の注意事項
3.3 多目的ツール
3.4 Bonnieを使ったディスクのベンチマーキング
3.5 その他のツール
3.6 いくつかのネットワークモニタリングツール
3.7 まとめ
第4章 Linux特有のツール
4.1 Linuxディストリビューションのsysstat
4.2 ktopとgtop
4.3 /procファイルシステムを使ってシステム活動を監視する
4.4 その他の無料のユーティリティ
4.5 まとめ
第5章 明確なボトルネックと 不明確なボトルネック
5.1 ボトルネックは常に存在する
5.2 ユーザの期待
5.3 パフォーマンスアグリーメント
5.4 CPUボトルネックのチューニング
5.5 明確なクラスタリングソリューション
5.6 カーネルにおけるCPU関連のパラメータのチューニング
5.7 ソフトウェアにおけるCPU関連のパラメータのチューニング
5.8 メモリでのボトルネック
5.9 結論
第6章 Window Systemのパフォーマンス
6.1 Xサーバのパフォーマンスの分析
6.2 結果の測定
6.3 ローカルで使うためのXサーバの チューニング
6.4 Xデスクトップのパフォーマンスチューニング
6.5 まとめ
第7章 ネットワーク パフォーマンス
7.1 ネットワークパフォーマンスの問題概要
7.2 ハードウェアによる方法
7.3 アプリケーションのネットワークチューニング
7.4 ドメイン(領域)を知ることの価値
7.5 Sambaのチューニング
7.6 NFSのチューニング
7.7 NISのチューニング
7.8 カーネルを変更してパフォーマンスを向上させる
7.9 ボンディング
7.10 強制的な帯域制限
7.11 新規の興味深い機能
7.12 高稼働率/ロードバランシング
7.13 ツール
7.14 結論
第8章 ジョブ制御
8.1 バックグラウンドモード
8.2 at機能
8.3 cronを使う
8.4 niceとrenice
8.5 まとめ
第9章 Linuxカーネル
9.1 カーネルとは
9.2 データ表示エリア
9.3 ネットワーク操作
9.4 仮想メモリ
9.5 カーネルの再コンパイル
9.6 まとめ
第10章 HTTPの動作
10.1 ディスク領域の管理
10.2 ディスクI/Oの利用
10.3 スワップによる戦略
10.4 RAIDの使用
10.5 ソフトウェアRAID
10.6 代替のソリューション
10.7 まとめ
第11章 Linuxおよびメモリ管理
11.1 物理的なRAM要件の判断
11.2 スワップ領域
11.3 スワップパーティション対スワップファイル
11.4 高度なトピック
11.5 まとめ
第12章 Linuxシステムサービス
12.1 「典型的な」inetd.confファイル
12.2 インターネットサーバ(inetd)
12.3 TCP Wrapper
12.4 rc.dスクリプト
12.5 まとめ
第13章 キャパシティ プランニングを考える
13.1 キャパシティプランニングとは?
13.2 従来のシステム要件
13.3 アプリケーションに特有の要件
13.4 構造化の手法
13.5 利用環境を考える
13.6 パフォーマンスチューニングとキャパシティプランニングの相互関係
13.7 チューニングの必要性に代わるプランニング
13.8 予測分析と実際の結果
13.9 キャパシティプランニングの必要性の評価方法
13.10 まとめ
第14章 キャパシティ プランニングの方法
14.1 キャパシティプランニングの青写真
14.2 一般的な原理
14.3 ソフトウェアおよびハードウェアの要件
14.4 構造の開発方法
14.5 将来的な柔軟性の保証
14.6 例
14.7 まとめ
第15章 ケーススタディ:Webサーバのパフォーマンス
15.1 Webサーバのパフォーマンス
15.2 典型的なメモリの問題
15.3 増加するネットワークの遅延
15.4 もう1つのメモリの問題
15.5 Linux Virtual Server(LVS)のウォークスルー
15.6 まとめ
第16章 今後の動向
16.1 World Wide Webのリソース
16.2 雑誌、ジャーナル、およびニュースレター
16.3 ニュースグループとメーリングリスト
16.4 まとめ
内容説明
Linuxのボトルネックの発見法からチューニング法、キャパシティ計画まで、幅広い知識をコンパクトにまとめて解説。カーネル2.4系にも対応。
目次
パフォーマンスチューニングの概要
パフォーマンスチューニングの側面
Linux用の一般的なUnixパフォーマンスモニタリングツール
Linux特有のツール
明確なボトルネックと不明確なボトルネック
X Window Systemのパフォーマンス
ネットワークパフォーマンス
ジョブ制御
Linuxカーネル
パフォーマンスのためのディスク構成
Linuxおよびメモリ管理
Linuxシステムサービス
キャパシティプランニングを考える
キャパシティプランニングの方法
ケーススタディ:Webサーバのパフォーマンス
今度の動向
著者等紹介
Fink,Jason R.[FINK,JASON R.][Fink,Jason R.]
1984年の高校時代にコンピュータを改良しようとして、その電源を破壊してしまったころから、コンピュータや電子工学にも関わるようになった。それ以来、メインフレームシステムやUnixで構成されたLANなど、興味深いネットワークやシステムで作業を行ってきた。また、さまざまな方法でオープンソースコミュニティに貢献している
Sherer,Matthew D.[SHERER,MATTHEW D.][Sherer,Matthew D.]
Apple2互換機が流行っていたころにLaser128でコンピュータにふれ、長い年月にわたってコンピュータに熱心に関わってきた。また、ペンシルバニア州HuntingdonにあるJuniata大学において、コンピュータサイエンスの学位を取得し、その過程でUnixやLinuxに出会った。大学を卒業後、しばらくの間は政府と契約していたが、ビジネスの世界に魅力を感じて、そちらへ移った。現在、オープンソースやフリーソフトウェアに関するあらゆる情報を追跡し、その効果を伝え、制限があるソリューションに代わって、それらが選択されるように多くの時間を割いている
岡田長治[オカダチョウジ]
1961年生まれ。1985年シャープシステムプロダクト入社、その後シーイーシーに転職。1989年に独立し、企業向けUnix業務システムの設計、構築、運用等の業務を始める。1994年には現在の有限会社エルアイコーポレーションを設立、現在代表取締役。その後は1985年よりインターネットに携わってきた経験を生かしインターネット関連のシステム構築、イントラネット業務システムの開発などを手がけるかたわら、国学院大学非常勤講師を務める
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。