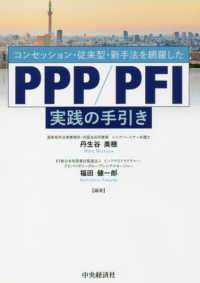出版社内容情報
女性のlife(人生)と胎児life(生命)の狭間で葛藤や対立が生じる妊娠中絶、他者の命の救済が人の死の判定にかかわる臓器移植の現在…。生と死、人の命と尊厳をめぐるさまざまな問題を具体的な事例から自分事として考える。
[目次]
第?部 知る・つかむ
第1章 妊娠中絶と出生前・着床前診断
1.妊娠中絶
コラム 米国における妊娠中絶問題
コラム 中絶における女性の自己決定権
コラム 「青い芝の会」と日本の障害者運動
2.旧優生保護法と強制不妊手術
コラム 障害とは何か
3.出生前診断
コラム 「トリソミー」とダウン症
4.着床前診断
コラム 「しょうがい」の表記について
コラム 共生社会を理解するためのキーワード
第2章 生殖医療
1.不妊治療
2.卵子提供
3.代理出産
4.AIDで生まれるということ
第3章 脳死と臓器移植
1.救世主きょうだいと臓器移植
2.臓器移植の歴史
3.日本の「臓器移植法」と臓器移植の現状
コラム 和田心臓移植事件
4.脳死をめぐる問題
5.「脳死臓器移植」の問題点
第4章 自己決定と終末期医療
1.生を〈まっとう〉すること
2. 患者の〈自己決定〉をめぐる諸問題――インフォームド・コンセント
3.終末期医療
4.安楽死
5.自己決定と死ぬ権利――エリザベス・ボービアの事例
第?部 深める・広げる
第5章 「人間の尊厳」と「パーソン論」
1.人間の尊厳
2.パーソン論
第6章 優生思想を超えて
1.相模原事件から考える
2. 人類は生物学的に〈改良〉できるのか――優生学の始まり
3.優生政策の各国での展開
コラム 人種は存在しない
コラム 悪の凡庸さ
コラム 人体実験を許すのは……
4.日本の優生政策
5.これからの倫理のために
第7章 死生学
1.死生学とその背景
2.人間に固有の死とは
3. 死と向き合い,死を受けとめる――代表的な死生学者による考察
コラム キューブラー=ロス
4. 死にゆくものへのケア――ターミナルケア,ホスピス
5. グリーフケア――故人との絆(強い結びつき)とは
6.悲嘆の経験は共有可能か
7.歴史のなかにおける死の捉え方の変容
8.医療化社会における死
9.死の文化のために
内容説明
自分、家族、大切な人のこと…医療技術の発達がつきつける難しい選択に本気で向き合うために。
目次
第1部 知る・つかむ(妊娠中絶と出生前・着床前診断;生殖医療;脳死と臓器移植;自己決定と終末期医療)
第2部 深める・広げる(「人間の尊厳」と「パーソン論」;優生思想を超えて;死生学)
著者等紹介
三崎和志[ミサキカズシ]
1963年生。東京慈恵会医科大学医学科教授
小椋宗一郎[オグラソウイチロウ]
1973年生。東海学院大学人間関係学部教授
林千章[ハヤシチアキ]
1953年生。女性学研究者、ライター(フェミニズム批評)
南孝典[ミナミタカノリ]
1975年生。國學院大学北海道短期大学部准教授
府川純一郎[フカワジュンイチロウ]
1983年生。岐阜大学地域科学部助教(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 電子書籍
- 【単話版】Nostalgia worl…
-

- 電子書籍
- 異世界最強の嫁ですが、夜の戦いは俺の方…