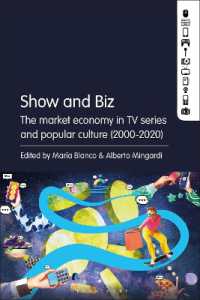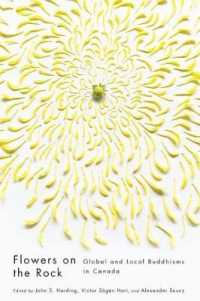出版社内容情報
《内容》 膨大な投資をせずに,利用者中心で地域も活性化できるケアマネジメント事業は可能だろうか? その答えは本書にあり! 医療・福祉・保健が一体となって,効率よくヒト・モノ・カネを動かす方法とその効果を,著者の考え方や具体的な事例とともに紹介。これからの在宅ケアに欠かせない一冊。
《目次》
chapter 1 ケアマネジメント事業の意義と役割
1 ケアマネジメント事業とは何か
2 ケアマネジメント事業が求められる背景
3 ケアマネジメント事業の目的
chapter 2 退院計画と地域連携
1 退院計画とは
2 退院計画のプロセス
3 退院計画を後押しする診療報酬改定
4 病院からの特養ホーム入所申請の増加:
新たな入所基準により安易な申請は不可能に
5 退院計画や連携を評価した診療報酬と介護報酬の具体例
6 退院計画を後方連携の戦略に
7 退院時ケアプランは「生活再構築プラン」
chapter 3 在宅医療にふさわしい物と技術
1 PEGによる在宅経腸栄養
2 在宅中心静脈栄養
3 膀胱留置カテーテル
chapter 4 新しい時代の痴呆性高齢者のケアマネジメント事業
1 痴呆性高齢者のケアマネジメントの現状と課題
2 痴呆ケアの切り札,グループホーム・宅老所・ユニットケア
3 痴呆ケアにはケアの場を超えた共通軸がある
4 痴呆ケアは小規模多機能事業所で
5 施設内ユニットケアのすすめ
6 新型特別養護老人ホームの誕生
chapter 5 超高齢時代の終末期ケア
1 新しい緩和ケアの概念とは
2 入院ケア中心に発展してきた緩和ケア病棟
3 一般病棟における緩和ケアの誕生
4 高齢者の終末期ケアのあり方
5 介護保険施設における終末期ケアの現状と課題
6 病院サポートチームと在宅緩和ケアの有機的連携
chapter 6 変わる高齢者住宅事業
1 「賃貸住宅」+「生活支援サービス」がセットされた新しいタイプの高齢者住宅
2 高齢者住宅が急増している理由
3 特定施設入所生活介護を届出ない理由
4 高齢者共同住宅
5 有料老人ホーム類似施設
6 変わる有料老人ホーム
7 二極化されるケアハウス
8 PFIを活用したケアハウス
9 新型特養,ケアハウス,有料老人ホームの違いがボーダレスに
10 新しい高齢者住宅の課題
資料 「高齢者の終末期医療」に関する日本老年医学会の「立場表明」
索引
内容説明
第1章は、高齢社会に求められるケアマネジメントサービスの意義と役割について、経済・医療・福祉の動向を踏まえながら問題提起。第2章では、退院計画や連携を評価する診療報酬・介護報酬を概説し、連携を促進するツールとして、連携クリニカルパス、ケアプラン共通軸について具体例を提示している。第3章は、『訪問看護と介護』(医学書院)誌上で1999年9月~2000年7月に「在宅医療にふさわしい物と技術」に連載されたものを加筆修正したもの。第4章は、痴呆ケアマネジメントについて、現状の課題を整理しながら、グループホームや宅老所など小規模多機能施設の整備を強調している。第5章では、緩和ケア病棟と在宅緩和ケアの有機的連携について、諸外国の制度を参考にまとめた。また、介護保健施設における終末期ケアの現状と課題を整理しながら、超高齢社会における終末期ケアのあり方について、若干の提案をした。第6章では、増加する中所得者層を対象とした、新しい高齢者住宅事業に注目した。
目次
1 ケアマネジメント事業の意義と役割
2 退院計画と地域連携
3 在宅医療にふさわしい物と技術
4 新しい時代の痴呆性高齢者のケアマネジメント事業
5 超高齢時代の終末期ケア
6 変わる高齢者住宅事業
著者等紹介
篠田道子[シノダミチコ]
日本福祉大学社会福祉学部助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。