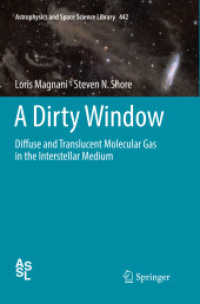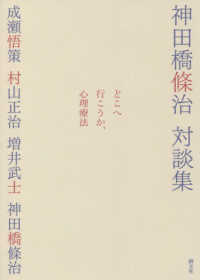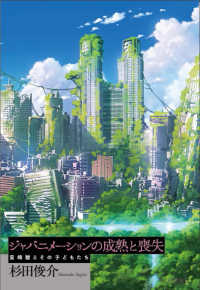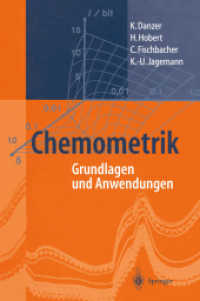出版社内容情報
三重県伊賀市にある窯元「土樂」。
自然の恵みの中のおおらかな暮らしを、四季折々の豪快なレシピとともに綴る。
家族を育み、客人の心を捉える至高の料理ともてなしは、ここから始まる。
第一章 囲炉裏のある暮らし
囲炉裏は馳走の原点/薄茶と菓子のおもてなし/花を生ける/掛け軸を飾る/囲炉裏は最高の調理場/酒宴の始まり
第二章 畑と里山のある暮らし
【春の畑・里山】春の恵みと仕事/春の料理(葉玉ねぎの天ぷら/鶏スープ煮/葉のぬた/小鯵の南蛮漬け ほか)
【夏の畑・里山】夏の恵みと仕事/夏の料理(焼きとうもろこし/丸ごと胡瓜と蒸し鮑/泥亀煮/鱧と松茸のしゃぶしゃぶ ほか)
【秋の畑・里山】秋の恵みと仕事/秋の料理(抜き菜と甘鯛のしゃぶしゃぶ/焼きねぎ/ほうれん草の抜き菜と香箱蟹 ほか)
【冬の畑・里山】冬の恵みと仕事/冬の料理(焼きかぶ/水菜と油揚げのすき焼き/伊賀牛の炭焼き赤芽芋の炊いたん/お漬けもん3種/壬生菜の卵とじ/抜きたて生葱/大根のきんぴら ほか)
第三章 陶器のある暮らし
土樂の黒鍋/土鍋をつくる/秋の火入れ/土樂の新作陶器/陶仏に祈りをこめる/白州次郎さん思い出の湯呑み
【著者紹介】
陶芸家。1944年生まれ。伊賀焼きの里として知られる、三重県伊賀市丸柱の窯元「?樂(どらく)」の7代目当主。伝統的な手びねりとろくろによって作られる陶器(特に黒鍋)は、政治・文化・芸能など各界の著名人から長年高い評価を受ける。また、「よく喰らい・よく飲み・よく笑い・よく眠り」がモットー。伊賀の山里の四季折々の花や木々を愛で、コメ・野菜を半自給し、川魚・山菜・キノコなど、自然の恵みを大らかに楽しむ生活を送る。
目次
第1章 馳走の原点 囲炉裏(花を活ける;茶を点てる;献立を考える;囲炉裏で饗す)
第2章 畑と里山 四季の恵みを食す(春;夏;秋;冬)
第3章 作陶とともにある暮らし(器は前に出ず、後ろに下がらず;野焼陶仏;表現方法は器と料理)
著者等紹介
福森雅武[フクモリマサタケ]
1944年、三重県伊賀・丸柱の代々「土樂」と称する窯元に生まれる。土樂窯七代目(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ナミのママ
へへろ~本舗
emiko