内容説明
食のデータベース「食MAP」を使って、日本の食卓に科学の光を当てる。日々の食卓は、無意識に働く習慣的な行動で形作られている。食卓づくりに影響を与えている文化的背景や、消費者の合理的な行動を明らかにしながら、日本の食卓を生態学的に分析した報告書。
目次
第1章 食卓の文脈を読む食卓考現学
第2章 飽食時代の次ぎに来る食の豊かさ
第3章 変わらない日本人の味覚
第4章 大都会の食卓に息づく郷土の味
第5章 食卓で立派に健在する旬と文化
第6章 日常に隠れた食卓の知恵
第7章 だれも知らないシングルスの食卓
第8章 食卓の10年トレンドと嗜好の変化
著者等紹介
齋藤隆[サイトウタカシ]
「株式会社ライフスケープマーケティング」取締役会長。1948年、香川県生まれ。日本リサーチセンター・総合研究所、NTTデータ通信を経て、2001年に同社を設立。自身が開発した食卓マーケティング情報システム「食MAP」を使い、食品メーカーの商品開発・営業支援、食品小売業の販売企画へのアドバイスや情報提供などの事業を展開する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
猫
1
地域別食のあるあるかと思ったけど、膨大なデータに基づいた、食に関するマーケティングの本。スーパーの仕入れ担当者さんとか、必読。
カエル子
1
もっと安易に笑って「へぇ~」を繰り返す中身を想像していましたが、意外にも、膨大なデータをもとに消費者の食卓実態を観察検証するマジメな本でした。2009年末の時点で、累計400万食卓、1,600万メニュー、4,000万食材のデータが蓄積されているというから食MAP恐るべし。しかも意外なデータもかなりありました。最長3年間、毎日の食卓情報をせっせと入力するという地味な作業をしてくれているモニター世帯が360もあるってことに一番驚きましたけど…。2012/08/01
katta
1
タイトルが悪い。日本人の食卓をシステマチックにきちんと取材した本なのに、全然伝わらない。その上、誤字脱字、送り仮名の間違いが多くて腹が立つ。これは編集者が悪い。食卓の崩壊はそんなにない、と言い切っているけれど、この人の「食マップ」をきちんと実施できる人は、かなりアッパークラスの人じゃないだろうか?少なくとも主婦の法則に当てはまる人がそういるとは思えない。2010/11/30
るき
0
食卓のマーケティングって面白いですね。岩村暢子さんの著書も読んでますが、こちらの方が前向きというか明るい分析です。シングル世帯をきちんと分析してるのは納得のデータ。しかし、こんな地道な調査に協力してくれる世帯ってことは、そもそもきちんとした食生活してそうだよなという気もします。2013/05/11
ヒヨドリスキ
0
家庭で購入した商品、料理の材料等を朝夕毎食調べたデータを元に家庭の食生活を考察した本。土日はご馳走だから月火は簡単又はリセット食で焼き魚って私も同じだった〜。後おでんは年3回ヤマがあるとか面白い。家庭食への関心が高まっているのも本当だろうと思う。ただ分析力から言うと『家族の勝手でしょ』には及ばないな。2012/09/04
-

- 電子書籍
- 悪喰魔辞典 18話
-

- 電子書籍
- メモリーハンター【タテヨミ】第48話 …
-
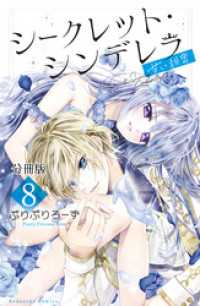
- 電子書籍
- シークレット・シンデレラ~甘い秘密~ …
-
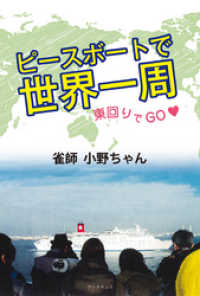
- 電子書籍
- ピースボートで世界一周 東回りでGO
-
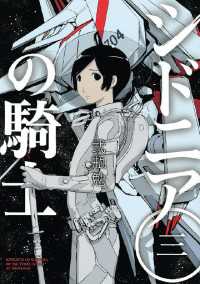
- 電子書籍
- シドニアの騎士(3)




