出版社内容情報
イギリスの児童文学にもイギリス文学史で言われる「キャノン(正典)」による「偉大な伝統」が形成されてきた。
いわゆる「名作」の歴史である。それに対し、本書が目指すのはそれとは異なるもう一つの「イギリス児童文学史」の試みである。
すなわち、「名作」として今日まで知られているもの以外に、どのような本が、どのような時代に、どれほど、どのように読まれたかが
問いとなる。
膨大な歴史資料から解明するイギリス近代の子供の読書世界。
内容説明
古い屋根裏部屋で埃をかぶる子供の本棚。イギリス近代の、今日では「忘れられた子供の本」が、当時の世相にいかに受け入れられたのか?膨大な史料を基に解明する、名作の系譜とは一線を画したイギリスの児童文学史。
目次
第1章 子供用の聖書の誕生―ジャン・フレデリック・オステルヴァルド『簡約聖書物語』(一七一二年あるいはそれ以前)他
第2章 ピューリタン後裔の子供の讃美歌―アイザック・ウォッツ『聖なる歌』(一七一五)
第3章 イギリス帝国の子供の物語―ジョン・ニューベリー刊『靴二つさんの物語』(一七六五)とその続編(一七六六)
第4章 「学者犬」の童謡―セアラ・キャサリン・マーティン『ハバードおばさんとその犬の滑稽な冒険』(一八〇五)他
第5章 子供の本における残酷性―ペロー童話、グリム童話の受容小史
第6章 妖精物語論争と近代的児童文学観の成立―『ジョージ・クルックシャンクの妖精文庫』(一八五三‐六四)
第7章 堕落しかつ無垢な子供たち―チャールズ・ディケンズの「子供の文学」
第8章 子供の現代生活の物語―ロバート・バーンズ挿絵『ストーリー=ランド』(一八八四)他
著者等紹介
鶴見良次[ツルミリョウジ]
筑波大学大学院博士課程文芸・言語研究科単位取得満期退学。ケンブリッジ大学ダーウィン・カレッジ客員研究員などを経て、成城大学文芸学部英文学科教授。博士(文学)。英語・イギリス文学専攻。著書に『マザー・グースとイギリス近代』(岩波書店、日本児童文学学会特別賞)ほか(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
志村真幸
Go Extreme
-

- 電子書籍
- アルバトロス・ビュー No.677 -…
-
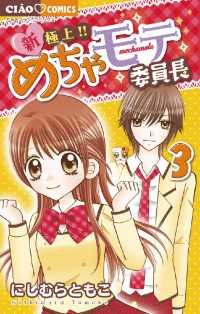
- 電子書籍
- 新・極上!!めちゃモテ委員長(3) ち…







