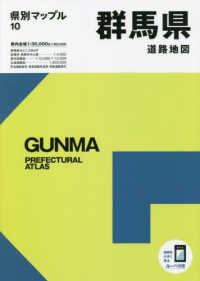目次
第1章 総論(民俗信仰とは)
第2章 生活のなかの神仏(家の神;山・海・里の生活にみる神々と祈願;諸職と神々;石の神仏)
第3章 社寺と講(神社と氏子;寺院と檀家;講と巡礼)
第4章 祈〓と神懸かり(巫女と信仰;ノロ・ユタと信仰;山岳信仰と修験)
第5章 社会不安と信仰(兆・占・禁・呪;疫神・流行神)
著者等紹介
新谷尚紀[シンタニタカノリ]
1948年広島県に生まれる。1971年早稲田大学第一文学部卒業。1977年早稲田大学大学院文学研究科史学専攻博士後期課程修了。国立歴史民俗博物館教授、総合研究大学院大学教授、國學院大學文学部教授を経て、國學院大學大学院客員教授。国立歴史民俗博物館名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。社会学博士(慶應義塾大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
noko
3
大学の教科書のような本。家を建てる時、暦で吉凶を調べたり、玄関やトイレ位置を風水で判断する。庶民も家相を見るようになったのは、18世紀からで関西が中心。19世紀に入り江戸でも。日本にはイタコ、ゴミソ、ユタなどと呼ばれる巫女がいる。イタコは口寄せが主な生業。本来盲目か弱視の女性が師匠の元で修行してなるが、最近晴眼のイタコもいる。東北にはゴミソという巫者もいて晴眼。イタコは減り、ゴミソは近年増えていて境界が曖昧に。沖縄にはユタなどがいる。戦前人心を惑わすとして弾圧されたが、今も続いている。日本の南北端にいる。2023/10/12
-

- 和書
- 苦しみの手放し方