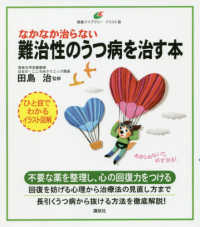目次
第1部 変貌する現代社会と語彙(言葉の性差の背景とゆくえ;待遇場面による語の選択;外来語の氾濫と定着;商品命名という言語行為)
第2部 メディアによる語彙の創造と広がり(作家による語彙の創造;アニメキャラクターの言葉;流行歌・Jポップの言葉―自己組織化現象としての日本語回帰;テレビ放送による言葉の広がり;新しいコミュニケーションツールとネット集団語)
第3部 語彙の規範と改良(医学用語の特徴と医療の言葉―漢字・日本語研究者および患者の視点から;裁判員制度の導入と司法の言葉;外国人のための「やさしい日本語」における言葉の基準;語彙はなぜ国語政策に取り上げられないのか)
著者等紹介
田中牧郎[タナカマキロウ]
1962年島根県に生まれる。1989年東北大学大学院文学研究科博士後期課程中退。2014年東京工業大学大学院社会理工学研究科博士後期課程修了。現在、明治大学国際日本学部教授。日本語学専攻。博士(学術)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かりんとー
6
最初の女性ことばの話、あとメディアと語彙のところが面白かった。面白くない(興味のない)ところは頭に入ってない。2024/05/06
Shinjuro Ogino
0
第1章(言葉の性差)は面白かったが、他の章は(私にとっては)冗長で面白くなかった。いわゆる女性言葉は、現代ではテレビドラマの中だけだという。特に女学生では「女性文末詞(だわ、のね等)は使われていない。文末詞の性差について、東京男性語、東京女性語、江戸男性語、江戸女性語(一般と上層)を比較した表がある(p7)。江戸上層女性語は特殊だが、東京男性/女性語は、全て江戸男性/女性語(一般)で性差なく用いられていた。女性の敬体使用は好まれる。 明治に登場した「てよ、だわ」は、当初よくない言葉だったが戦後転換した。2020/10/05
-

- 電子書籍
- 妖精姫が復讐を決めたわけ 2話「新しい…