出版社内容情報
人間や動物の行動をデータからどう読みとるか。行動計量学の考え方・技法・実例を初歩から解説〔内容〕データとは/確率の意味/統計の基本概念/グラフ化/測定値/スケーリング/分類/確率モデル/データによる現象解析/調査の科学/他
【目次】
1. 行動計量学とデータ
1.1 行動計量学
1.2 データとデータ解析
1.3 対象をいかに把握するか
1.4 標識づけについて
1.5 データによる現象解析の順序
2. 確率のもつ意味
2.1 確率とは何を意味するか
2.2 試行を根底において確率の数学的定義
2.3 統計の意味
2.4 確率と統計の結びつき
3. 調査対象集団・母集団・標本の認識の重要性
3.1 確率と統計の結びつきという観点から
3.2 調査対象集団・母集団・標本
4. チェビシェフ型不等式の意味
4.1 チェビシェフの不等式の確率論的意味
4.2 チェビシェフの不等式の高性能化 その1
4.3 チェビシェフの不等式の高性能化 その2
5. 多次元空間における分散
5.1 散らばりと一般化分散
5.2 多次元にチェビシェフ型不等式と集中楕円・一般化分散
6. 判別尺度の種々相と判別尺度としての相関比
6.1 判別尺度の種々相
6.2 相関比
6.3 多次元の場合の相関比
6.4 相関比の応用としての線型判別関数
6.5 ベクトル相関
7. 判別尺度としての判断成功率
7.1 判断成功率
7.2 判断成功率と相関比η2との関係
7.3 多次元の場合
8. 距離と一般化分散
8.1 距離と分散
8.2 マハラノビスの距離
9. グラフ化の意味
10. データにおける測定誤差と測定値変動の分析上の意味その1―量の場合
10.1 測定誤差・測定値変動と線型・非線型
10.2 測定値が数量である場合
11. データにおける測定誤差と測定値変動と分析上の意味その2―質の場合
11.1 実 例
11.2 偏りの出方について
11.3 誤差を考慮して正しい結論を導き出す方法
11.4 誤差を考慮して正しい結論を導き出す方法その2―関連分析の場合
11.5 回答確率の推定
11.6 回答確率推定の実例
12. データにおける量と質―スケーリングの方法
12.1 量と質
12.2 リッカートスケール
12.3 ガットマンスケール
13. クロス表による分析と推論の陥穽―多次元データ分析における鍵となる考え方
13.1 集団表章と個人表章
13.2 多次元的推理の重要性
13.3 考えの筋道
13.4 クロス表に基づく推論の陥穽 その1
13.5 クロス表に基づく推論の陥穽 その2
14. 分類・クラスター化とそのための尺度のあり方
14.1 一般的考察
14.2 分類の基本概念
14.3 分類の諸方法
14.4 その他の考察
15. 確率モデルによるデータ解析の意味―潜在構造分析
15.1 潜在構造分析の基本的考え方と方法
15.2 仮定の特性化
16. 調査の行動計量学的あり方―調査の科学へ
16.1 調査の論理
16.2 操作的と論理的―調査の二つの柱
16.3 調査は実態ではない
16.4 測られたものの意味
16.5 調査の二つの立場
16.6 調査の評価
16.7 医学における例示
16.8 逐次近似の発想
16.9 社会調査は一つの道具
16.10 問題発見の論理
16.11 仮説―検定の考え方の限界
17. 日本人の国民性研究と時系列調査
17.1 国民性調査の全般的構想
17.2 国民性の表現をどう考えるか
18. 意識の国際比較と連鎖的比較調査分析法(CLA)―CLAはいかにして生まれたか
18.1 比較の行動計量学的方法論
18.2 意識の比較研究の目的
18.3 比較研究の基本的立場
18.4 CLAの方法
18.5 データの分析
18.6 現在我々の行っている研究
19. 患者のQOLと治療の科学化
19.1 状態の表現
19.2 最適の条件
19.3 最適制御の一例
19.4 最適制御の手段としての治療
19.5 科学的治療法の確立へ
20. 跋―データに対する情熱の大切さ
21. 参考文献
22. 索 引
目次
序 行動計量学とデータ
第1部 行動計量学的観点から見た統計学の諸概念(確率のもつ意味;調査対象集団・母集団・標本の認識の重要性;チェビシェフ型不等式の意味;多次元空間における分散;判別尺度の種々相と判別尺度としての相関比 ほか)
第2部 行動計量学におけるデータ分析(グラフ化の意味;データにおける測定誤差と測定値変動と分析上の意味;データにおける量と質―スケーリングの方法;クロス表による分析と推論の陥穽―多次元データ分析における鍵となる考え方 ほか)
第3部 行動計量学的考え方に基づく「データによる現象解析」(調査の行動計量学的あり方―調査の科学へ;日本人の国民性研究と時系列調査;意識の国際比較と連鎖的比較調査分析法―CLAはいかにして生まれたか ほか)
-
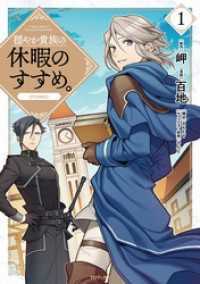
- 電子書籍
- 穏やか貴族の休暇のすすめ。@COMIC…
-
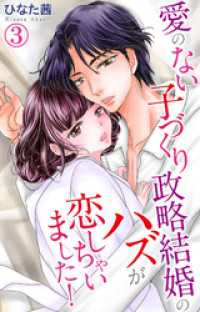
- 電子書籍
- 愛のない子づくり政略結婚のハズが恋しち…
-
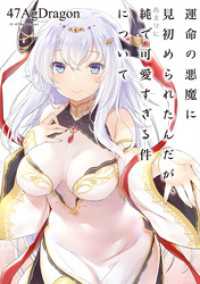
- 電子書籍
- 運命の悪魔に見初められたんだが、あまり…
-
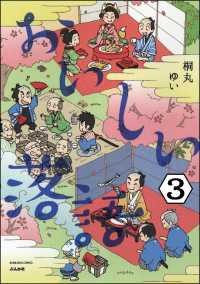
- 電子書籍
- おいしい落語(分冊版) 【第3話】




