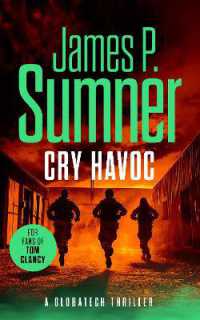出版社内容情報
“理系学生の実状と関心に沿った”コンパクトで実用的な案内書。〔内容〕コミュニケーションと表現/ピタゴラスの定理の表現史/コンポジション/実験報告書/レポートのデザイン・添削/口頭発表/インターネットの活用
【目次】
1. コミュニケーションと表現
1.1 はじめに
1.2 コミュニケーション・モデルと発話意図
1.3 トップダウンの情報処理とフィードバック
1.4 コミュニケーションと文化の関係
2. ピタゴラスの定理はどのように表現されてきたか
2.1 ピタゴラスの定理とその証明
2.2 数学の日本語表現と菊池大麓
2.3 三辺の関係から面積の関係を導く
3. コンポジションから理科系の作文を考える
3.1 コンポジションをとりあげる理由
3.2 文章作成の技法
3.3 特徴をとらえる視点
3.4 事実と意見
4. 学生実験の報告書を書く
4.1 何を書くか
4.2 報告書を書く
4.3 実験レポートに望ましい文章、避けるべき文章
5. レポートをデザインする
5.1 書くこととデザインすること
5.2 パラグラフの作り方
5.3 ビジュアルの作り方
5.4 全体のレイアウトと仕上げ
6. 口頭発表の要点
6.1 口頭発表の方法
6.2 口頭発表の内容
6.3 言葉以外の表現
7. 学生のレポートを添削する
7.1 卒論を添削する
7.2 口頭発表を添削する
8. レポート作成にインターネットを活用する
8.1 インターネットについて
8.2 メール
8.3 WWW(World Wide Web)
9. おわりに
10. 索 引
【編集者】
栗 山 次 郎
【著者】
岡 本 良 治, 大 橋 健
栗 山 次 郎, 向 後 千 春
小 谷 享, 菅 隆 明
中 川 慎 二, 山 本 信 也
柳 沢 浩 哉, 楊 子 江
内容説明
本書は、いままで文書や口頭での発表について深く意識してこなかった人を読者として想定しています。そのために、「書く」、「語る」、「表現する」などの事柄についても基本的な説明をしています。「表現」に関しても、例示でも「理科系」にとらわれず筆を進めた部分もあります。日常生活でわかりやすい表現を目ざす努力をしていれば、その成果はレポートや論文に必ず反映します。スムーズに理解される記述についての知識でも、それをうまく活用する契機がなければ、忘れられていきます。知識が技法を洗練し、練習に支えられた技術が知識を豊かにします。本書は知識と技法の両方を高めるよう構成しました。
目次
1 コミュニケーションと表現
2 ピタゴラスの定理はどのように表現されてきたか
3 コンポジションから理科系の作文を考える
4 学生実験の報告書を書く
5 レポートをデザインする
6 口頭発表の要点
7 学生のレポートを添削する
8 レポート作成にインターネットを活用する
-
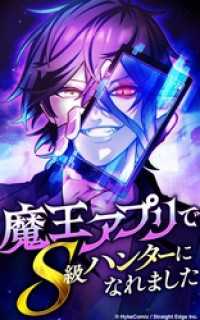
- 電子書籍
- 魔王アプリでS級ハンターになれました【…
-
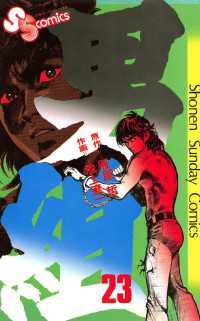
- 電子書籍
- 男組(23) 少年サンデーコミックス