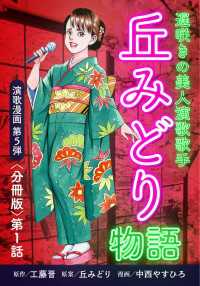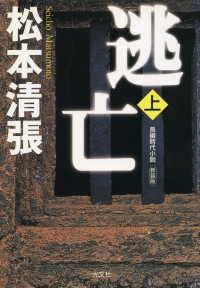内容説明
愛情が伝わらないジレンマを抱えている先生、サポートに自信をなくしている先生―。そんな先生に役立つように、複数のこどものキーパーソンとなるための具体的な手立てを本書では紹介しています。
目次
第1章 「愛着の問題を抱えるこども」の理解と支援(「愛着障害・愛着の問題」と「発達障害」の関係と違い;「愛着の器」モデルに基づく愛着修復プログラム;通常の学級における「愛着の問題を抱えるこども」への支援方法・かかわり方)
第2章 教室の中の「愛着障害」支援の実際(通常の学級に在籍している愛着の問題を抱えたこどもたち;通常の学級における愛着の問題を抱えたこども朝日くんへの支援;通常の学級担任が、複数の愛着の問題を抱えたこどものキーパーソンになり得るか ほか)
第3章 「愛着の問題」と「発達障害」との関係(発達障害そのものの分類が混乱;発達障害の診断;発達障害、愛着障害 ほか)
著者等紹介
米澤好史[ヨネザワヨシフミ]
和歌山大学教授
松久眞実[マツヒサマナミ]
桃山学院教育大学教授
竹田契一[タケダケイイチ]
大阪医科薬科大学LDセンター顧問。大阪教育大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。