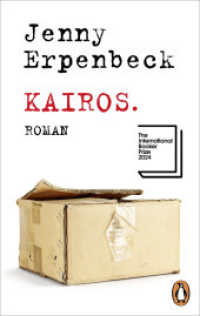目次
第1章 国語の学習に必要な足腰を鍛える
第2章 アクティブ・ラーニングをつくる単元計画
第3章 ゼロから学べる「話すこと・聞くこと」の授業づくり
第4章 ゼロから学べる「読むこと」の授業づくり
第5章 ゼロから学べる「書くこと」の授業づくり
第6章 ゼロから学べる伝統的な言語文化と国語の特質にふれる言語活動
第7章 ゼロから学べる板書&ノート指導
著者等紹介
青木伸生[アオキノブオ]
1965年千葉県生まれ。東京学芸大学卒業後、東京都の教員を経て現在筑波大学附属小学校教諭。全国国語授業研究会会長、教育出版国語教科書編著者、日本国語教育学会常任理事、國學院栃木短期大学非常勤講師、筑波大学非常勤講師、早稲田大学非常勤講師を兼任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 公爵家のSランク神器使いの回帰 第18…