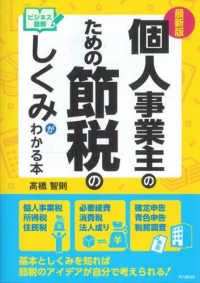内容説明
算数が苦手な子どもに共通する3つのこと、10までの数の分解と合成が重要なわけ、わり算が難しい3つの理由、答えの見積もりは4年生からでは遅い、ものさしとコンパスを上手に使うコツ…etc.知れば知るほど、授業がうまくなる。
目次
第1章 授業づくりの基本にかかわる6のこと(算数授業をよくするための5つの学習規律;「なぜ算数を学ばないといけないの?」と問われたら ほか)
第2章 数と計算の授業にかかわる17のこと(数と計算指導の3つの要点;数の学習は生まれたときから始まっている ほか)
第3章 量と測定の授業にかかわる9のこと(量と測定指導の3つの要点;ものさしを使わない必然性を生み出す ほか)
第4章 図形の授業にかかわる9のこと(図形指導の3つの要点;立体図形の仲間分けに込められた重要な指導事項 ほか)
第5章 数量関係の授業にかかわる9のこと(数量関係指導の3つの要点;低学年で伴って変わることを指導することの意味 ほか)
著者等紹介
黒田恭史[クロダヤスフミ]
大阪教育大学大学院修士課程修了、大阪大学大学院博士後期課程修了。博士(人間科学)。大阪府内の公立小学校教員として8年間勤務し、その後、佛教大学講師、助教授、准教授、教授の後、現在、京都教育大学教授。小学校教員、中・高等学校数学教員養成に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 電子書籍
- 花は朽ちてもあなたは残る【タテヨミ】第…
-
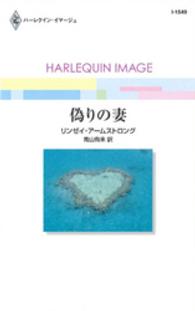
- 電子書籍
- 偽りの妻