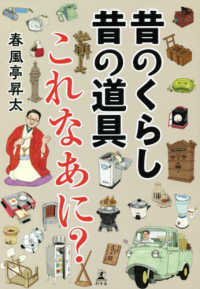内容説明
音読を「指導」、していますか?理論×実践で分かる子どもが伸びる指導の在り方。
目次
第1章 音読の意義と音読指導への提言(音読の意義とは;なぜ、今「音読指導」なのか1 「指導」しているとは言えない現状;なぜ、今「音読指導」なのか2 誰でも取り組めて、成長が分かりやすく、達成感を得やすい ほか)
第2章 学力が高まる!クラス全員で取り組める音読指導システム(音読時の姿勢;音読指導の基本的な流れは「範読」→「追い読み」→「○読み」である;音読指導のスタートは「範読」から ほか)
第3章 必ず押さえたい音読指導技術&楽しく力がつく学習活動(指導技術1 追い読みは2、3文字かぶせる;指導技術2 「目ずらし」を指導する;指導技術3 個別評価の際の声かけは「厳しくも温かく」 ほか)
著者等紹介
土居正博[ドイマサヒロ]
1988年、東京都八王子市生まれ。創価大学教職大学院修了。川崎市公立小学校に勤務。国語教育探究の会会員(東京支部)。全国大学国語教育学会会員。国語科学習デザイン学会会員。全国国語授業研究会監事。教育サークル「深澤道場」所属。教育サークルKYOSO’s代表。『教師のチカラ』(日本標準)編集委員。2018年、読売教育賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
み
13
音読に関しては「時間がない」という理由で授業中に取り扱うことが少なかったが、本書を読んで次年度からもっと本腰を入れて取り扱うべきだなと感じた。「教科書が読めない子どもたち」を読んで、子どもたちに読解力を付けなくてはと思い、今年度読書教育を進めようと思っていたのだが実を結ばず、悩んでいたので、国語の学習の中で耳で聞くことによってできたかできてないかがはっきり分かる音読から頑張ってみよう。音読→黙読で読めるようになったらきっと、読書も進んでいくと思うんだよな2022/03/13
家主
5
49B 自分の学校では、「張りのある声で読む」「、で休み。で止まる」「正確に読む」を、音読の学級掲示として全クラスに貼り、指導を求めている。土居先生の主張と自分の考えが近いことがわかり、さらに自信を持って音読指導ができると思った。学校全体にも情報発信し、掲示物を貼っているだけにならないようにしていきたい。暗唱までさせたことがないので、2学期から暗唱にチャレンジできるシステムを作りたい。基準を持って、厳しくも温かい指導を続けていきたい。学びの上限を取っ払い、音読のレベルをまだまだ上げてやりたい。2021/08/11
家主
3
19B 再読。再確認。範読→追い読み ①ハキハキ②正しく③スラスラで評価。C.B.A.A○.A◎.S.S○.S◎の8段階評価にしようと思う。暗唱チャレンジ。つっかえたらダメ読みは、A◎読みチャレンジとしよう。1分間高速読み。15秒間超高速読みは、定番化したい。2022/05/02
-
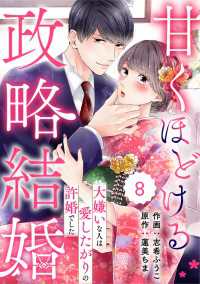
- 電子書籍
- comic Berry's 甘くほどけ…