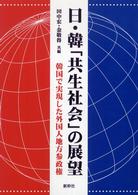- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
内容説明
タブレットPCやスマートフォンに対する関心が高まるとともに、学校教育の中でも利用の可能性を探る動きが活発です。しかし、これまでのパソコンと同じように導入すれば、何を目的とするのか位置づけも不明確なままとなってしまいます。そうならないためにも、操作インターフェースが簡単であるというタブレットPCやスマートフォンの利点を最大限に活用すれば、何らかの困難さを抱える子どもたちにとって大きな役割を果たすと考えられます。本書では、これらのツールの意義や具体的活用法について詳述し、さらに子どもたちの新しい能力を活かす社会へつなげる教育についても論じています。
目次
1 タブレットPCやスマホで何が変わるか?
2 アクセシビリティ障害のある子どもがタブレットPCを使うには
3 電子書籍とタブレットPC・スマホ
4 タブレットPC導入のポイント
5 なぜタブレットPC利用をためらうのか?―タブレットPCへの不安をとく
6 子どもが安全安心にタブレットPCやスマホを活用できる環境
7 これからの子どもの能力 新しい能力を認める教育へ
著者等紹介
中邑賢龍[ナカムラケンリュウ]
1956年山口県生まれ。東京大学先端科学技術研究センター人間支援工学分野教授
近藤武夫[コンドウタケオ]
1976年長崎県生まれ。東京大学先端科学技術研究センター人間支援工学分野講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さなごん
5
1年積んであってようやく読み終えた。タブレットがあるから使う、のではなくなぜタブレットが必要かを考えなければならない。2014/08/01
ぴーたん
4
タブレットをどう特別支援教育に生かしていくか書いた本。読み書き障害があり書字では全く読めない字を書く小学生がテキスト入力ではしっかりと自分の考えを示すことができていることが紹介されていて驚き。発達の凸凹があるとできないところを見てできるはずだと繰り返し練習させたりすることが良くある。それよりも近視の子がメガネをかけるように発達障害障害の子にサポートツールを使えるようにして欲しいです。マインドマップも考えをまとめるのにいいんだね。利用させる時の注意、ゲームアプリは入れないなども細かく書かれています。2013/07/11
epitaph3
4
iPadなどタブレットを教育に、主に、障害がある人向けに、タブレットがどう可能性を広げてくれるかを述べている本。肝はやはり合理的配慮。タブレットで差が生まれるのではなく、能力差を埋める、社会を生きやすくする。そのためのツールとして考えることができる。文字多めだが、ぜひぜひ、読んでほしい。しかしなあ、社会で一番頭が固いのは、学校だな。そう思う。社会に出たらタブレットで便利生活OKなのに、学校では「ずるい」「努力をしなくなる」という理由でタブレットはダメ…というのはなあ。2013/05/29
だとじう
0
特別支援教育とか合理的配慮とか。市情視研ではアプローチしていない視点。来年度、この視点での実践もあるといいな。@yonda42016/01/31
碧子
0
障害により困難なことや発達の凸凹や苦手なことを助けるものとして、素晴らしい可能性を持ったものだと思う。正しい使い方や本人に合った方法を習得することで、本人も周囲も生活しやすくなり可能性も広がるし、自信にもつながる。具体例もあがっていてとても興味深かったです。「できないなら人より努力しろ」「みんな同じでないといけない」「そのような機器を持ち込むことで差別になる」というような方たちの考えはどうすれば動かすことができるのでしょう。「目の悪い子にとっての眼鏡」本当だな。よく分かります。2015/09/05