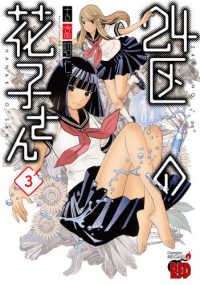出版社内容情報
「武士」はいかにして「朝廷」と決別し、日本の統治者となったのか。約五百年間続く武家政権の始まりを人気歴史学者がやさしく解説。
内容説明
約六百五十年間続く武士の世はいかにして始まったのか?日本の統治者であった「朝廷」は、なぜ「幕府」にその座を譲ったのか?平氏らの失敗に学び、京都ではなく、鎌倉で独立を果たした頼朝の決断が歴史を大きく変えた―。4つのターニングポイントから、武家政権の誕生について、人気歴史学者がわかりやすく解説する。
目次
第1章 足利義満「日本国王」の権力―1392年(明徳3年)(公家を凌駕する存在へ;「祭祀権」と「課税権」を奪う ほか)
第2章 足利尊氏「京都」に挑む―1336年(建武3年)(得宗専制と幕府の揺らぎ;御家人の不満が幕府を倒した ほか)
第3章 北条時頼万民統治への目覚め―1253年(建長5年)(武士は危険な収奪者だった;支配して気づいた己の未成熟さ ほか)
第4章 源頼朝「東国」が生んだ新時代―1180年(治承4年)(「イイクニ」つくろう?;暴力装置としての武士 ほか)
著者等紹介
本郷和人[ホンゴウカズト]
1960年東京都生まれ。東京大学史料編纂所教授。東京大学・同大学院で石井進氏、五味文彦氏に師事し、日本中世史を学ぶ。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
saga
37
室町時代から、鎌倉・室町まで遡って、武士のルーツを考察する。欲を言えば江戸時代から始めてほしかったが、焦点を中世に絞ったということだろう。朝廷のある京都に政治の中心を据えた足利尊氏と、関東に残って朝廷と距離を置いた源頼朝の比較が面白い。義経が朝廷から直接任官されたことに対する頼朝による討伐は、武士団を統率するうえで避け得ない事だったと理解できた。政治能力が劣化した朝廷・公家に代わって武士が台頭したのだが、幕末には逆の現象が起きた。さて、現代の政府はいかがだろう……2020/02/10
金吾
22
武士の世がどのようにしてできていったのかを室町から鎌倉に遡りながら説明しています。武士たちが学んでいったことを武家が統治者として成長した原因としているのは当たり前の話なのかもしれないながら成る程と思いました。2025/11/17
ちさと
21
約600年続いた武士の世はいかにして始まったのか。本書は、中世の前半、すなわち平安末期から室町時代を①義満②尊氏③北条時頼④頼朝と、ターニングポイントを起こした人物に焦点を当て時間をさかのぼりながら、時代に要請された武士の変貌の様と武家政権の成り立ちを検証していくもの。やっぱりその原点である頼朝はすごいな。京都の公家勢力に不満を募らせた残虐そのものの「武士団」を統制し、それらの土地所有を保証=武家政権を実質的に成立させる。その抜群の政治的才能の裏には、非常に猜疑心が強く、冷淡な性格があったとか。2025/06/07
perLod(ピリオド)🇷🇺🇨🇳🇮🇷🇵🇸🇾🇪🇱🇧🇨🇺
3
本来は暴力を行使し税の取立て役だった武士がいかにして行政官=政治家へと変わっていったかというテーマに絞った小著で、ターニングポイントを遡って叙述する。 第1章:足利義満。 義満は南北朝統一して天皇から祭祀権と徴税権を奪い、これが「象徴天皇制」の始まりとする。また対外的には「日本国王」を名乗り外交権も掌握。天皇は完全に「いるだけ」になった。「戦国時代の天皇には権力や権威はあったか?」という論争があるが、本章を読む限り権力は完全になくなっている。→2024/08/09
石光 真
1
義満、尊氏、時頼、頼朝とさかのぼる。NHKさかのぼり日本史⑧の新書化。 時頼は百姓を略奪的に搾取する野蛮な暴力集団である武士を、公家に代わる統治者にするために御成敗式目とともに撫民を説いた。ただ同じ武士では説得力が足りないので、鎌倉五山を開き、坐禅を組ませ、神仏の力で武士を訓育し、やがて統治者たらしめた。2024/08/31
-
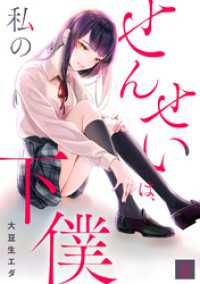
- 電子書籍
- せんせいは、私の下僕【フルカラー】(2…
-
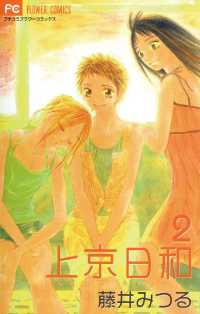
- 電子書籍
- 上京日和(2) フラワーコミックス